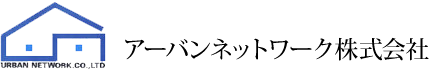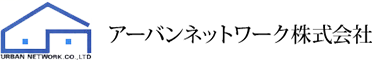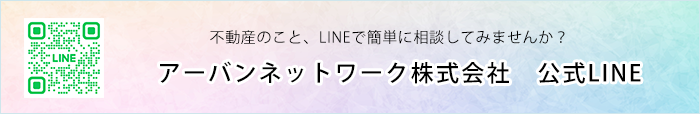ブログ
BLOG
2021.02.23
不動産コラム
賃貸経営をしている方は、住宅をどのように管理されているでしょうか。
様々な管理方法がありますが、どのような管理方式が良いのかわかりませんよね。
本記事では管理委託と一括借り上げについてご紹介します。
どのような管理形式があるかご存じでない方はぜひご覧ください。
□管理委託と一括借り上げとは
まずはじめに本記事でご紹介する2つの管理方式は、どのような管理形式であるかについてご紹介します。
管理委託とは、入退去、募集リフォーム等賃貸経営の業務全般を管理会社に委託する管理方式です。
賃貸経営の管理業務はその範囲が広いため、経験豊富な不動産会社に委託することで円滑な経営が行えます。
また、一括借り上げとは、不動産会社や管理会社がオーナーが所有している不動産を一棟丸ごとなど一括で借り上げる管理方式です。
また、この管理方式はサブリースとも言います。
上記では一棟丸ごとと述べましたが、この管理方式では必ずしも一棟丸ごとではないため、どのように契約するかは不動産会社と相談して決めてください。
□違いとは
上記では管理委託と一括借り上げとはどのような管理方式であるかについてご紹介しました。
上記を読み、違いはないのではないかとお思いの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、両者にも違いはあります。
本記事では、管理委託と一括借り上げの違いについて3つご紹介します。
1つ目は、契約する人の違いです。
管理委託ではオーナーと入居者との間で賃貸借契約書を結びますが、一括借り上げでは管理会社と入居者との間で結びます。
つまり、管理委託ではみなさんが入居者と契約を毎回結ぶ必要がありますが、一括借り上げでは全て任せられます。
2つ目は、家賃保証の違いです。
管理委託では家賃保証が基本的にありませんが、一括借り上げでは査定賃料の約80〜90パーセント保証されています。
また、一括借り上げでは契約日から約2カ月の免責期間が設けられており、その期間は入居者募集期間として収入がないため、注意してください。
入居者が賃料を滞納している場合に関しても、委託管理では回収されるまで支払われませんが、一括借り上げでは保証されています。
3つ目は、管理会社に対する手数料の違いです。
管理委託では家賃の3〜10パーセントですが、一括借り上げでは10〜20パーセントを手数料として管理会社である不動産会社に支払う必要があります。
具体的な数字に関しては不動産会社や契約内容によって異なるため、あくまで参考としてください。
□まとめ
本記事では管理委託と一括借り上げとはどのような管理形式であるか、両者の違いについてご紹介しました。
それぞれ依頼する不動産会社によって、契約内容は大きく異なることがあるため注意してください。
また、当社は米子市にて不動産会社として活動しているため、賃貸経営についてお悩みがある方はお気軽にご相談ください。
2021.02.19
不動産コラム
一戸建て住宅を賃貸経営しようとご検討中の方はいらっしゃいませんか。
使用しなくなった住宅があるため、賃貸として貸し出そうとご検討中の方もいらっしゃるでしょう。
しかし、戸建ては儲かるのか不安であるという方もいらっしゃると思います。
そのため、本記事では戸建て住宅の賃貸経営についてご紹介します。
□戸建て住宅は儲かるのか
はじめに、戸建て住宅の賃貸経営は儲かるのかどうかについて解説します。
やはり、賃貸経営をするうえで気になるのが収益をあげられるかどうかですよね。
戸建ての賃貸経営をしようとされている方の中には、戸建ては儲からないと聞き不安に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、近年では賃貸ニーズの多様化によって戸建ての賃貸需要が高まってきています。
そのため、結論としては十分儲けられます。
メリットとしては以下の点が挙げられます。
1つ目は、競合が少ないことです。
戸建ての賃貸は競合が少ないため、入居希望者が比較的見つかりやすいです。
また、先ほども述べたとおり現在は賃貸ニーズが多様化しており、戸建てのニーズは高まっています。
2つ目は、入居期間が長いことです。
戸建てに住む方は比較的長く住む傾向があります。
ご家族で住まれる方が多いため、子供が成人するまで引っ越さないという方もいます。
入居期間が長いということは、その期間は空室が発生せず収益が確保できます。
また、リフォームをする回数が減るため、支出も抑えられます。
3つ目は、将来売却もできることです。
戸建て賃貸は上記でも述べた通り長く住まれる方が多いため、入居者からそのまま購入したいといった申し出も多いです。
□戸建ての注意点について
上記では戸建ては儲かりやすく、メリットも多いことをご紹介しました。
しかし、戸建て経営にも注意するべきことがあります。
1つ目は、空室や家賃滞納のリスクが大きいことです。
入居者を確保しやすいのが戸建てのメリットですが、もし空室になってしまった場合は収益がゼロになってしまうというリスクもあります。
アパートなどでは1部屋でも入居者がいると収益は発生しますが、戸建てではゼロになってしまうため早めの入居者確保が重要です。
2つ目は、金利上昇時の負担が大きくなることです。
戸建て経営ではローンの金利が上昇した際に手元に残る金額が少なくなります。
現在の日本は比較的金利が低いですが、楽観視できる要素とは言えないでしょう。
そのため、可能であれば固定金利のローンを借りるようにしましょう。
□まとめ
本記事では、戸建て住宅は儲かるのか、また戸建て経営の際の注意点についてご紹介しました。
戸建て住宅を賃貸として貸し出そうとしている方は、ぜひ参考にしてください。
また、当社は米子市で不動産会社として活動しているため、何かわからないことがございましたらお気軽にご相談ください。
2021.02.15
不動産コラム
空き家をお持ちの方は、空き家を放置してしまうと固定資産税が高額になってしまうことをご存じでしょうか。
空き家をお持ちの方でも、そのことを知らないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、対策をすることで無駄な出費を抑えられます。
そのため、本記事では空き家の固定資産税についてご紹介します。
□空き家を放置すると
空き家をお持ちの方は、しっかりと管理をされているでしょうか。
現在日本では空き家の放置問題が深刻化しており、その数は年々増加しています。
そのため、政府はそのまま放置されることで倒壊あるいは保安上危険となる恐れのある状態または衛生上有害となる恐れのある状態などにある空き家を特定空き家として認定しています。
この特定空き家が、固定資産税が高くなる理由です。
具体的には、上記のような放置されている空き家は特定空き家として認定されると、本来の特例の適用が外され、その空き家の固定資産税が最大6倍にまで跳ね上がります。
つまり、本来受けられていた特例を特定空き家として認定されることで、特例適用外となってしまい固定資産税が高額になってしまいます。
□対策について
上記では、空き家を放置すると固定資産税が非常に高額になるとご紹介しました。
ではどのような対策をすれば良いのでしょうか。
まずは売却するという方法です。
空き家の状態が良いという方は、売却することをおすすめします。
しかし、空き家の状態が良い場合でも人口の少ない田舎にその空き家がある場合は、売れるまでに時間がかかる可能性があるため注意してください。
次は賃貸物件として貸し出すことです。
空き家を賃貸物件とすることで、固定資産税が高額になってしまうことを防げるうえに家賃収入が得られます。
しかし、賃貸物件として貸し出すためにはある程度の設備を整える必要があるため、場合によってはリフォームする必要があることをご理解ください。
また、不動産会社に賃貸経営を委託する管理委託という方法もあるため、ご興味のある方はぜひ一度不動産会社に相談してみましょう。
次に、親族の誰かが住むことです。
親族などの信頼できる人を住まわせることで、空き家ではなくなり特定空き家に指定される心配もなくなります。
しかし、親族の方の生活なども考慮して、本当に親族の方にとっても良いことなのか判断してから住んでもらいましょう。
□まとめ
本記事では、空き家の固定資産税についてご紹介しました。
空き家は放置すると固定資産税が高額になるため、できるだけ早めに対策しましょう。
また当社は米子市にて不動産会社として活動しているため、何かお困りの方はお気軽にご相談ください。
2021.02.11
不動産コラム
賃貸経営をされている方は、確定申告の際には青色申告がおすすめであることをご存じでしょうか。
しかし、確定申告についてあまりご存じでない方もいらっしゃると思います。
そのため、本記事ではなぜ青色申告がおすすめであるか、またその注意点について米子市の不動産会社である当社がご紹介します。
□青色申告とは
まずは、青色申告とはどのようなものであるかご紹介します。
青色申告とは確定申告の一種であり、条件を満たすことで申請できます。
青色申告には節税のための様々な優遇制度があり、さまざまなメリットがあります。
1つ目は、特別控除です。
青色申告をすることで、10万円の控除が受けられます。
また、事業の規模が大きいと判断された場合は、最大で65万円の控除も受けられます。
そのため、そこまで事業の規模が大きくない方にとっても、大きい方にとっても有り難い制度といえるでしょう。
2つ目は、経費に計上できる範囲が広いことです。
具体的には、減価償却費や、修繕費、損害保険料、租税公課、人件費、管理費など、非常にたくさんの項目を経費として計上できるため、税金で取られる額が低くなります。
またアパートやマンションを経営されている方は、条件を満たせば青色事業専従者給与を必要経費に計上できます。
配偶者に給与を支払っている方は、経費として計上できるため、その分所得の申告を少なくできます。
□青色申告をする際の注意点について
上記では青色申告のメリットについてご紹介しました。
しかし、青色申告を行うためには条件などがあります。
そのため、本記事では次にその条件についてご紹介します。
まずは、青色申告を行うためには所得税の青色申告承認申請書を税務署へ提出する必要があります。
提出期限は、青色申告を行う年の3月15日までです。
この申請を行わなければ青色申告は行えないため、申請し忘れることのないよう注意してください。
次に、記帳方法に関する条件です。
青色申告の場合は複式簿記での記帳が必須であり、売り上げや経費などを複式簿記で記帳し、損益計算書と貸借対照表を作成する必要があります。
また、帳簿や請求書などは確定申告書の提出期限から7年間保存する必要があることも注意してください。
次に貸付規模に関する条件です。
上記でご紹介した65万円の控除を受けるためには、事業的規模として認可される必要があります。
具体的には、独立家屋である場合は概ね5棟以上の貸付、またアパートやマンションである場合は概ね10室以上の賃貸が可能な独立した部屋があることで認可されます。
□まとめ
本記事では、賃貸経営における青色申告についてご紹介しました。
青色申告は有効活用することで非常に便利な制度となりますが、注意するべきことも多いためぜひ専門家に相談して行いましょう。
2021.02.07
不動産コラム
空き家をお持ちの方は、しっかりと維持されているでしょうか。
空き家を放置される方が増え、日本の空き家問題が深刻化しています。
また、空き家は通常の住宅より傷むのが早いと言われているため、しっかりと維持することが重要です。
本記事ではなぜ空き家は劣化が早いのか、また劣化を軽減させる方法についてご紹介します。
□空き家は劣化が早い
上記で述べたように空き家は一般的に通常の人が住んでいる住宅より劣化が早いと言われています。
では、なぜ劣化が早くなってしまうのでしょうか。
本記事ではその原因として考えられていることを3つご紹介します。
1つ目は、換気などによる空気の入れ替えが行われないことです。
人が生活している場合は、さまざまな方法で換気が行われます。
しかし、空き家の場合は換気が行われず、空気の流れが生じません。
そのため、梅雨時期などには湿気がこもりカビなどが繁殖しやすくなり、住宅の基礎部分の木材を腐らせてしまいます。
2つ目は、掃除がされないことです。
人が生活している場合は定期的な掃除が行われますが、空き家の場合は掃除がされなくなり、チリやほこりがたまりやすくなります。
そして、それらを餌とする虫やカビが繁殖します。
特にカビなどは換気がされない中湿度が高くなってしまうことで、一気に繁殖してしまいます。
3つ目は、修繕されないことです。
人が生活している場合は雨漏りや地震などで住宅の一部が損傷した際は修繕がすぐに行われますが、空き家の場合は損傷箇所が放置されてしまいます。
そのため、損傷箇所から雨風が侵入し劣化速度を早めてしまします。
□劣化を軽減させるためには
上記ではなぜ空き家の劣化が早いのかについてご紹介しました。
次に、どのようにして劣化を軽減させるかについて、その方法を3つご紹介します。
1つ目は、定期的な換気を行うことです。
上記でもご紹介したとおり、換気をして空気の流れを生じさせることで劣化の速度は遅らせられます。
具体的には、1カ月に1回は換気をするようにしましょう。
ご自身で換気を行うために通えないという方は、管理会社の方に依頼しましょう。
2つ目は、定期的に通水することです。
水道管に溜まっている水を全て流すことで、水道管のサビを洗い流せます。
具体的には、家中の蛇口をひねって1分ほど水を流しっぱなしにしてください。
また、水道に関しては解約してしまうと水を流せなくなるため、可能な限り契約は残しておきましょう。
3つ目は、定期的なメンテナンスを行うことです。
具体的には、定期的な清掃や修繕を行ってください。
劣化の状態がひどい場合は、リフォームや売却などを視野に入れましょう。
□まとめ
本記事では空き家がなぜ劣化しやすいのか、劣化を軽減させる方法についてご紹介しました。
定期的な換気、通水、メンテナンスを行って、少しでも長く維持できるようにしましょう。
また、当社は米子市で不動産会社として活動しているため、空き家についてお困りの方はお気軽にご相談ください。
2021.02.04
不動産コラム
賃貸経営されている方は、成功するためにはコツがあることをご存じでしょうか。
近年副業として注目されている賃貸経営ですが、コツを押さえることでより経営がしやすくなります。
そこで本記事では、賃貸経営する際のコツについてご紹介します。
□賃貸経営で成功するためのコツとは
賃貸経営を成功させるためのコツについて、本記事では5つご紹介します。
これから賃貸経営を始められる方、既に始めているけれどうまくいっていない方は、ぜひご覧ください。
1つ目は、土地選びについてです。
土地選びの際の重要なポイントは、まずターゲットとなる入居者像を明確にすることです。
ターゲットを明確にすると、入居者のニーズを押さえやすく、入居者同士の紹介につながるメリットがあります。
また、似たような境遇の方が住んでいるため、ターゲットを定めていない住宅より空室率を抑えられるでしょう。
2つ目は、空室対策についてです。
空室対策の具体的な方法は、人気の高い立地に住宅を立てる、借り手にマイナスと評価される箇所を修繕する、広告に力を入れる、入居者の要望に真摯(しんし)に向き合うことが挙げられます。
空室対策は、みなさんの状況だけでなく、どのような場所にあるのか、築年数は何年なのかをはじめとした条件によって異なるため、空室対策する際は一度専門家に相談しましょう。
3つ目は、会社選びについてです。
成功させるためには、パートナーとなる不動産会社の力も必要です。
そのため、依頼する会社は慎重に選ぶようにしましょう。
また、その際にイメージや口コミだけで決めるのでなく、企画提案力や対応の良し悪しなど総合的に評価することをおすすめします。
4つ目は、税金控除についてです。
利益を出すためには、税金の控除を活用することが重要です。
具体的には、確定申告の際に白色申告から青色申告に変更すると控除が受けられます。
また、経費にできるものをあらかじめ調べておくことも大切でしょう。
税金についてご自身で調べている際に、ご不明な点がございましたら当社までご相談ください。
5つ目は、出口戦略についてです。
出口戦略とは、賃貸経営をいつまで行うかの計画を指します。
賃貸経営で成功される方の特徴の1つが、この出口戦略をしっかりと持っていることです。
手放すタイミングとしては、大掛かりな修繕が必要である時、空室期間が長い時、物件価格が高騰している時などがありますが、絶対的なタイミングは存在しません。
そのため出口戦略についてお悩みの方は、一度不動産会社に相談してみましょう。
□まとめ
今回は、賃貸経営で成功するためのポイントについてご紹介しました。
本記事では簡易的にご紹介しましたが、実際に賃貸経営される方は、専門家にしっかり相談して計画を立てると安心でしょう。
また、当社は米子市で不動産経営のサポートをしておりますので、お気軽にご相談ください。
2021.01.31
不動産コラム
アパート経営されている方で、「アパート経営は儲からない」と聞いたことがある方はいらっしゃいませんか?
アパート経営が本当に儲かるのか不安な方も少なくないでしょう。
そこで本記事では、米子市の不動産会社がアパート経営は儲かるのか、経営におけるコツは何かをご紹介します。
□アパート経営は儲からないのか
結論から述べると、アパート経営は儲かりづらいです。
そして、儲からない場合にはある程度の明確な原因があります。
本記事では、儲からない理由を3つご紹介します。
1つ目は、立地が悪い場合です。
アパート経営において、空室は最大のリスクと言えますが、立地が悪い場合は空室が多くなる傾向にあります。
そのため、既に土地をお持ちの方でアパート経営されたい方は、その土地が経営に優れているか確認することをおすすめします。
2つ目は、設計に問題がある場合です。
アパート建築は、ほとんどの場合でハウスメーカーによって行われます。
この際、ハウスメーカーによる設計が必ずしも1番儲かるものではないことに注意しましょう。
例えば、ハウスメーカーの規格品に多いのはファミリータイプですが、アパート経営を検討している方の中にはワンルームを希望される方も多いでしょう。
そのため、ハウスメーカーに設計を依頼する際は、ご自身による確認や必要に応じた修正をおすすめします。
3つ目は、自己資金が十分にない場合です。
アパートは築年数が経過することで、賃料の低下や空室の増加が発生します。
そのため、リフォームによって空室対策することが多いですが、その際に十分な自己資金を準備する必要があります。
自己資金が足りなくなる事態を防ぐためには、資金計画を見直しておくと良いでしょう。
□アパート経営で儲かるには
では、アパート経営で儲かるためにはどのようなことに注意すれば良いのでしょうか。
ここからは、儲かるためのポイントについてご紹介します。
1つ目は、環境変化に応じた設計をすることです。
具体的には、将来的な世帯構造の変動を考えることが重要です。
例えば、日本はファミリー世帯が減り、単身世帯が増えていくと予想されています。
そのため、これからは単身世帯を狙った間取りにすると良いかもしれません。
2つ目は、適切な管理方式を選ぶことです。
アパートの管理方式には、大きく分けて管理委託とパススルー型サブリース、家賃保証型サブリースの3種類あります。
それぞれが異なる管理方式であるため、しっかり吟味した上でご自身のライフスタイルに一番適しているものを選ぶと良いでしょう。
3つ目は、自己資金を十分に準備することです。
上記でも触れましたが、儲かるためには自己資金が十分に用意されていることが重要です。
具体的には、建築費の約30〜50パーセントを用意しておくのが理想的だと言われています。
□まとめ
本記事では、アパート経営は儲かるのかどうか、儲かるためのポイントについてご紹介しました。
儲かるためには、ポイントを押さえておくことが重要です。
当社は米子市で不動産経営をサポートしておりますので、何かご不明点がある方はお気軽にご相談ください。
2021.01.27
不動産コラム
賃貸経営をされていて、入居率を上げるために苦労している方はいらっしゃいませんか。
入居率が下がってしまうと収入が減ってしまうため、なんとか上げたいですよね。
しかし、入居率ばかりを気にし過ぎてしまうと、賃貸経営はうまく行かないでしょう。
本記事ではその理由と理想的な入居率についてご紹介します。
□入居率が高いだけではダメ
既に賃貸経営されている方だけでなく、これからしようとお考えの方でも入居率の重要性はご存じかと思います。
具体的には、毎月の家賃収入は入居率に大きく左右されるため、高い入居率を維持することが重要です。
しかしここで注意する点は、家賃収入がそのままご自身の収入になるわけではないことです。
その理由は、賃貸経営における収入は、家賃収入から経費などを差し引いた金額であるためです。
つまり経費が多くかかっている場合は、入居率が低い場合と同じ程度の影響が出てしまいます。
そのため、安定的な経営を行うためには、入居率だけではなく経営にかかるコスト、経費を抑えることが重要です。
□理想的な入居率とは
まず、理想的な入居率についてご紹介する前に入居率の考え方を解説します。
入居率とは、入居中の部屋が全体の部屋数に占める割合を指します。
上記では、入居率が高いだけでは賃貸経営はうまくいかないことをご紹介しました。
もちろん、入居率が高いに越したことはありませんが、100パーセントを維持し続けることは難しいと言えるでしょう。
では、どの程度の入居率を保っていれば良いのでしょうか。
理想的な入居率は、竣工から経過している期間によっても異なるでしょう。
例えば、竣工から5年目までは90〜100パーセントが理想的な入居率だと言えます。
これを下回る場合は、経営を始める前の準備が不十分であった可能性を考えましょう。
次に、10年目までは80〜90パーセント、20年までは70〜80パーセントを維持するのが理想的だと言われています。
上記で紹介した程度の入居率を維持できていれば、利回りを確保できるでしょう。
また、入居率と同様に大切なのが空室率です。
退去が決まってから次の入居者が決まるまでの空室期間が半年以上続いてしまうと、年間収支に大きく影響するでしょう。
□まとめ
本記事では、入居率の高さだけでは賃貸経営がうまくいかない理由と理想的な入居率についてご紹介しました。
賃貸経営をされる方は、入居率も気にしつつその他のことにも目を向けるようにしましょう。
また、当社は米子市で不動産経営のサポートをしておりますので、お気軽にご相談ください。
2021.01.23
不動産コラム
賃貸経営をお考えの方は、賃料や賃貸借契約書の他にも保険について考える必要があります。
万が一のときに保険に入っていないと、大きな損失を被ってしまうでしょう。
ここでは火災保険について解説しているので、米子市で賃貸経営を検討している方はぜひ参考にしてください。
□火災保険について解説
火災保険の補償の対象となるのは、火災による被害だけではないことをご存じでしょうか。
火災保険にも種類がありそれぞれ補償の範囲は異なりますが、一般的には以下のような被害が火災保険の補償の対象に含まれています。
例えば、落雷、爆発による被害があります。
これから自然災害が増えることを考えると、風災、雪災、水災による被害も補償の対象に入っていることはありがたいですね。
これだけではなく、集団による暴力や盗難の被害も補償に含まれています。
プランにもよりますが、火災保険はこれだけ手厚く補償してくれます。
賃貸経営を考えている方は、火災保険へ加入しておくことが無難であると言えるでしょう。
また、日本の法律では隣家の火事によるもらい火が必ずしも賠償されないということをご存じでしたか。
もらい火による火災は、重大な被害にならない限り、賠償責任を追及できません。
つまり、被害者であるにもかかわらず自分で補修費用を負担する必要があるのです。
このようなケースに備えるためにも、火災保険に入っておくことをおすすめします。
□火災保険のプランを選ぶ際のポイントについて解説
火災保険にはいくつかプランがあり、プランによって補償の範囲が変わってきます。
最低限の補償で良い方は、補償の対象が少ないプランを選ぶでしょう。
反対に災害が不安な方は、補償の対象が多いプランを選ぶかと思います。
ここでは、火災保険のプランを選ぶ際のポイントについて解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
プランを選ぶ際は、賃貸経営するエリアの環境を考慮する必要があります。
例えば、地域のハザードマップが役立つでしょう。
具体的には、近くに大きな川があれば、氾濫する可能性を考える必要があります。
高台に位置しているのであれば、床下浸水の心配はないかもしれません。
地域によっては、雪による事故や凍結の被害を考える必要があるでしょう。
ただし、ご自身の不注意による被害であるとみなされた場合は、火災保険の補償の対象外となることもあるので気をつけましょう。
補償の範囲について詳しく知りたい方は、専門業者に一度相談することをおすすめします。
□まとめ
火災保険が補償してくれるのは、火災による被害だけではないのですね。
賃貸経営する方は、土地や物件の状態、自然環境などを考慮して、火災保険のプランを選ぶと良いでしょう。
米子市で保険についてお困りの方は、お気軽に当社にお問い合わせください。
2021.01.19
不動産コラム
不動産相続に税金がかかることをご存じでしたか。
あらかじめ税金を把握しておくと、予期せぬ支払いに戸惑わずに済むでしょう。
そこで今回は、米子市の不動産会社が不動産相続にかかる税金についてお話しします。
□相続の際に支払う税金とは?
ここでは、不動産を相続する際に支払う必要がある税金の種類をご紹介します。
*登録免許税について
不動産を相続すると、所有地や面積をはじめとして、相続した不動産の情報を登記する必要があります。
その一環として、不動産の所有者を変更する「所有権移転登記」をしますが、その際にかかる税金が「登録免許税」です。
登録免許税は、固定資産評価額に0.4パーセントをかけると計算できます。
この際、固定資産評価額は市町村や年によって異なるため、注意しましょう。
登録免許税は原則現金で納付しますが、オンラインで申請する際は電子納付も可能です。
現金納付する方は、金融機関で必要書類を記入後、その場で登録免許税を支払いましょう。
その後、手続きした際に受け取った領収証書を、所有権移転登記の申請書に貼り付けます。
最後に申請書を登記所に提出して手続き完了です。
また、納付額が30,000円以下の場合は、収入印紙を使って納付できます。
収入印紙を使う方はまず、金融機関で納付する金額分の収入印紙を購入しましょう。
その後、登録免許税納付用台紙に購入した収入印紙を貼り付け、提出します。
上記では、納付額が30,000円以下の場合に収入印紙を使えるとご紹介しましたが、例外もあります。
そのため、詳しい納付方法についての不明な点は、法務局に問い合わせることをおすすめします。
*相続税について
相続税は、遺産相続が一定額を超える時に支払う税金を指します。
遺産を相続した際は、遺産総額から法律で定められた「基礎控除額」を差し引き、それに相続税を課税した額を支払います。
今まで相続税を支払う際は、現金一括納付が原則でした。
しかし、平成29年からオンライン上でのクレジットカード払いが可能になりました。
この際、支払い上限額が決まっていたり、手数料が発生したりするデメリットに注意しましょう。
□相続税には特例がある
ここまでは、不動産相続にかかる税金の種類をご紹介しました。
実は、相続税には控除が適用される場合があることをご存じでしたか。
ここでは、そのような特例をいくつかご紹介します。
1つ目は、小規模宅地等の特例です。
これは、土地に関する相続税控除の1つで、相続税を計算する際に必要な土地の評価額を下げる方法を指します。
最大80パーセント減額できますが、そのためには厳しい適用要件を満たす必要があります。
例えば、宅地要件や取得者要件、手続き要件がそれに当たります。
2つ目は、配偶者に対する税額の軽減です。
具体的に、配偶者には「1億6000万円」または「法定相続分相当額」のいずれか多い金額までは相続税がかかりません。
この他にも、生前贈与や相続時精算課税制度、未成年者や障害者に対する控除があります。
それぞれの方法には要件が定められているため、気になる方は詳しく調べることをおすすめします。
□まとめ
今回は、不動産相続にかかる税金についてご紹介しました。
初めて不動産相続を経験する方も多いかと思います。
税金の種類や特例を知っておくことで、スムーズな手続きができるでしょう。
不動産についてご不明な点がございましたら、お気軽に当社までお問い合わせください。
お問い合わせ
CONTACT
「悩みがある・困っている・売りたい、買いたい」
何でもご相談ください!