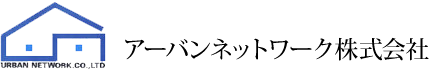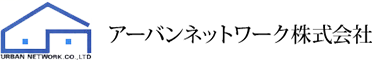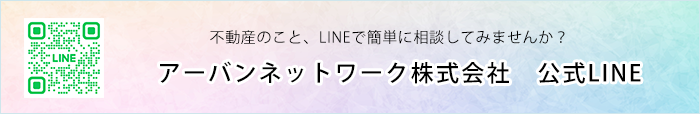ブログ
BLOG
相続放棄後も住み続けられる?リスクと対策を解説
不動産コラム
2025.11.01
みなさん、こんにちは!
米子市不動産売却を行っておりますアーバンネットワーク株式会社です!
長年の経験と豊富な知識を活かし、お客様の大事な住宅の売却をサポートいたします。
ここでは、不動産に関するお役立ち情報をご紹介いたしますので、ぜひご覧ください。
相続放棄は、複雑な手続きと様々なリスクを伴うため、十分な理解が必要です。
特に、相続放棄後も自宅に住み続けることを希望する場合は、居住継続に係る法的リスクや問題点を事前に把握しておくことが重要です。
相続放棄後も住み続けるとどうなるか
相続放棄の効果と住居の権利関係
相続放棄を行うと、相続開始前に遡って相続人の資格を失います。
これは、相続財産を一切承継しないことを意味しますが、相続放棄後も、当該不動産に居住し続けることは、必ずしも不可能ではありません。
ただし、相続放棄によって、相続財産である不動産に対する権利義務関係は、相続放棄者から相続人に移転します。
そのため、相続放棄者は、所有権を有する者ではなくなり、居住の法的根拠を失う可能性があります。
既に居住している場合でも、その権利の根拠を改めて検討する必要があります。
例えば、使用貸借契約を結ぶ、または、新たな居住権を設定するといった方法が考えられます。
居住継続における法的リスクと問題点
相続放棄後も居住を継続する場合、大きなリスクとして、債務の責任や、所有権移転にかかる手続き上の問題点が挙げられます。
相続財産に債務が含まれる場合、相続放棄によって債務の責任を免れることができますが、相続放棄後も当該不動産に住み続ける限り、その不動産に係る債務(例えば、抵当権に基づく債務、固定資産税など)との関連性を完全に排除することはできません。
また、所有権が移転するまでの間、不動産の管理や維持にかかる費用負担の問題も発生する可能性があります。
相続財産における居住権と使用貸借
相続財産に含まれる不動産について、相続放棄後も居住を継続したい場合、相続人と協議の上、使用貸借契約を締結する方法や、居住権を設定する方法などが考えられます。
使用貸借契約は、所有者から借りる形で居住を継続できる契約で、比較的簡素な手続きで成立します。
一方、居住権は、所有者の承諾を得て、一定期間、または無期限で、当該不動産に居住する権利を主張できる制度です。
ただし、居住権を設定するには、公正証書を作成するなど、より厳格な手続きが必要です。
相続放棄後の住居問題 具体的なリスクと対策
債務における責任範囲と免責事項
相続放棄は、債務の責任を免れる効果を有しますが、相続放棄後も居住を継続する場合は、注意が必要です。
仮に、相続財産に抵当権が設定されている場合、その抵当権は、相続放棄後も不動産に留まり、所有権を取得した相続人が債務を負うことになります。
相続放棄者は、債務の支払義務から免除されますが、住居の明け渡しを求められる可能性があります。
所有権移転の手続きと期間と費用
相続財産である不動産の所有権は、相続放棄によって相続人に移転します。
その手続きには、相続人の確定、遺産分割協議、所有権移転登記などが含まれ、数ヶ月から数年かかる場合もあります。
費用としては、弁護士や司法書士への依頼費用、登記費用などが発生します。
税金や光熱費などの費用負担と法的根拠
相続放棄後も居住を継続している間、固定資産税、都市計画税、水道光熱費などの費用負担が発生します。
これらの費用負担の法的根拠は、使用貸借契約や居住権の設定、もしくは、相続人との間の合意に基づきます。
明確な合意がない場合は、トラブルに発展する可能性があります。
相続放棄後の住居に関するトラブル解決策
相続放棄後の住居に関するトラブルを回避するために、事前に相続人との間で、居住条件、費用負担、期間などを明確に合意しておくことが重要です。
合意が得られない場合、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
相続放棄後も住み続けたい場合の注意点と手続き
相続人と債権者との交渉と合意形成
相続放棄後も居住を継続するには、相続人や債権者との交渉と合意形成が不可欠です。
相続人との間で、使用貸借契約や居住権の設定について合意し、その内容を明確に文書化しておくことが重要です。
債権者との間では、債務の状況や支払い方法について交渉し、合意を得る必要があります。
住居の売却や賃貸借契約などの選択肢
相続放棄後、居住を継続することが困難な場合、住居の売却や賃貸借契約を検討する必要があります。
売却する場合、不動産の市場価格を把握し、適切な価格で売却できるよう、不動産会社などに相談することが重要です。
賃貸借契約を結ぶ場合は、契約内容を十分に確認し、トラブルを回避する必要があります。
専門家への相談の重要性
相続放棄は複雑な手続きを伴い、専門的な知識が必要となります。
相続放棄後も居住を継続する場合、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。
専門家の助言を得ることで、法的リスクを軽減し、円滑な手続きを進めることができます。
相続放棄後の生活設計と住居確保のポイント
相続放棄後も安心して生活を送るためには、住居確保だけでなく、経済的な計画も立てる必要があります。
収入、支出を把握し、将来にわたる生活設計を立て、必要に応じて年金や生活保護などの制度を活用することも検討しましょう。
まとめ
相続放棄後も自宅に住み続けることは、法的リスクや手続き上の複雑さを伴います。
債務の責任、所有権移転、費用負担など、様々な問題が発生する可能性があるため、相続人や債権者との交渉、そして専門家への相談が不可欠です。
使用貸借契約や居住権の設定、住居の売却や賃貸借契約といった選択肢を検討し、自身の状況に最適な方法を選択することが重要です。
事前に綿密な計画と準備を行い、安心して生活を送れるよう、的確な対応を心がけましょう。
ご自宅や相続した物件、空き家など保持しているけれど活用できていないなどのお悩みございませんか?
アーバンネットワークでは、お客様の声に寄り添った提案でスムーズに売却までお手伝いいたします。無理強いや、お客様のお気持ちに添わない金額の引き下げなどは一切行いませんので、ご安心くださいませ。
お電話でのお問い合わせは 0859-30-2468 まで、
またはお問い合わせページからもご連絡いただけます。
皆さまからのお問い合わせを心よりお待ちしております。
お問い合わせ
CONTACT
「悩みがある・困っている・売りたい、買いたい」
何でもご相談ください!