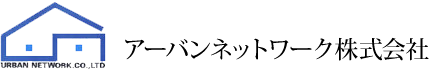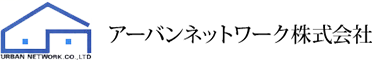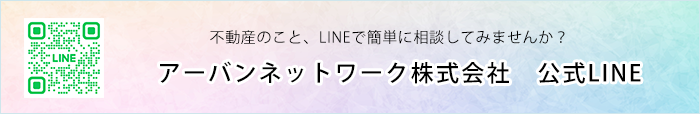ブログ
BLOG
税制改正で変わる!空き家相続・売却時の特例と注意点
不動産コラム
2025.08.15
みなさん、こんにちは!
米子市不動産売却を行っておりますアーバンネットワーク株式会社です!
長年の経験と豊富な知識を活かし、お客様の大事な住宅の売却をサポートいたします。
ここでは、不動産に関するお役立ち情報をご紹介いたしますので、ぜひご覧ください。
空き家の相続、悩んでいませんか?
特に、税金のこととなると、複雑な制度に戸惑ってしまう方も多いのではないでしょうか。
相続した空き家を売却する際に利用できる空き家の譲渡所得の特例は、節税に大きく貢献する制度ですが、その要件や手続きは複雑で、変更点も多いです。
スムーズな売却に向けて、ぜひこの記事を参考にしてください。
2023年度の税制改正により、空き家の譲渡所得の特例における控除額に重要な変更がありました。
従来は、相続人の人数に関わらず、譲渡所得から3,000万円を控除することができました。
しかし、改正後は、相続人が3人以上の場合は控除額が2,000万円に減額されます。
相続人の人数によって控除額が変わることを理解し、事前に控除額を正確に計算することが重要です。
複数人で相続する場合は、この変更点を踏まえた上で売却計画を立てる必要があります。
以前は、空き家の譲渡時に耐震基準を満たしているか、もしくは譲渡までに解体工事を完了していることが条件でした。
そのため、相続人は譲渡前に費用を負担して耐震改修工事や解体工事を行う必要があり、大きな経済的負担となっていました。
しかし、2023年度の税制改正により、この条件が緩和されました。
譲渡後、譲渡年の翌年2月15日までに耐震基準を満たす改修工事の完了または解体工事の完了を証明できれば、特例を受けることができるようになりました。
譲渡後、買主が改修や解体費用を負担するケースでも特例の適用が可能になった点は大きなメリットと言えます。
空き家の譲渡所得の特例を適用するには、確定申告が必要です。
必要な書類は、譲渡所得の金額の計算に関する明細書、被相続人居住用家屋等確認書など、複数あります。
さらに、相続開始前、期間、譲渡時など、様々な条件を満たしていることを証明する書類も必要となります。
具体的には、被相続人の住民票の除票、相続人の住民票、被相続人の居住用家屋の登記事項証明書、売買契約書のコピー、耐震基準適合証明書、家屋取壊し後の閉鎖事項証明書などが求められる場合があります。
これらの書類は、税務署に提出する必要があります。
事前に必要書類をリストアップし、漏れがないように準備することが重要です。
不明な点があれば、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
この特例制度は、増加する空き家問題の解決を目的としています。
老朽化した空き家は、防災上のリスクや景観の悪化につながるため、その有効活用を促進することが重要です。
この制度は、相続により空き家を相続した人が、それを売却する際に、譲渡所得から一定額を控除できるというものです。
これにより、売却を促進し、空き家問題の解消に貢献しようとする制度です。
特例制度の適用には、いくつかの条件があります。
まず、相続開始直前まで被相続人が居住していたこと、昭和56年5月31日以前に建築された戸建て住宅であること、相続開始日から3年以内に譲渡すること、譲渡価格が1億円以下であることなどです。
また、譲渡する建物は、耐震基準を満たしているか、または譲渡後一定期間内に解体されている必要があります。
これらの条件をすべて満たしている必要があります。
条件を満たしていないと、特例は適用されませんので、注意が必要です。
特例を適用するには、確定申告を行う必要があります。
確定申告書には、譲渡所得の金額の計算に関する明細書や被相続人居住用家屋等確認書などを添付する必要があります。
確認書は、市区町村役場に申請して取得します。
申請には、相続関係を証明する書類や、家屋の状況を示す書類などが必要となるため、事前に準備しておきましょう。
また、必要書類の提出期限にも注意が必要です。
期限までに必要な書類をすべて揃えて、税務署に提出しましょう。
相続人の人数によって控除額が異なります。
相続人が1人または2人の場合は3,000万円の控除が受けられますが、3人以上の場合は2,000万円に減額されます。
相続人が複数いる場合は、この点を考慮して売却計画を立てる必要があります。
また、相続税の申告と譲渡所得税の申告をどのように行うかについても検討が必要です。
この特例は、他のいくつかの特例と併用できます。
例えば、「自己の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」や「自己の居住用財産の買換え等に係る特例措置」などです。
ただし、併用できる特例とできない特例があるので、注意が必要です。
特に、相続税の取得費加算の特例とは併用できません。
どのような特例と併用できるのか、専門家に相談することをお勧めします。
申請にあたっては、各条件を満たしているか、必要書類をすべて準備しているかなどを十分に確認することが重要です。
些細なミスが、特例適用を妨げる原因となる可能性があります。
また、譲渡契約書に、税制改正後の特例適用に関する事項を明記しておくことも重要です。
事前に税理士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることで、トラブルを未然に防ぎ、スムーズな手続きを進めることができます。
2023年度の税制改正により、空き家の譲渡所得の特例制度に変更がありました。
特に、相続人の人数と控除額の関係、耐震基準と解体に関する条件の緩和は、売却を検討する上で重要なポイントです。
売却を検討する際は、これらの変更点を理解し、必要書類を漏れなく準備して、確定申告を行う必要があります。
適切な手続きを行うことで、節税効果を最大限に活かし、相続手続きを円滑に進めることが可能です。
この制度を活用して、空き家問題を解決し、相続手続きをスムーズに進めましょう。
ご自宅や相続した物件、空き家など保持しているけれど活用できていないなどのお悩みございませんか?
アーバンネットワークでは、お客様の声に寄り添った提案でスムーズに売却までお手伝いいたします。無理強いや、お客様のお気持ちに添わない金額の引き下げなどは一切行いませんので、ご安心くださいませ。
お電話でのお問い合わせは 0859-30-2468 まで、
またはお問い合わせページからもご連絡いただけます。
皆さまからのお問い合わせを心よりお待ちしております。
米子市不動産売却を行っておりますアーバンネットワーク株式会社です!
長年の経験と豊富な知識を活かし、お客様の大事な住宅の売却をサポートいたします。
ここでは、不動産に関するお役立ち情報をご紹介いたしますので、ぜひご覧ください。
空き家の相続、悩んでいませんか?
特に、税金のこととなると、複雑な制度に戸惑ってしまう方も多いのではないでしょうか。
相続した空き家を売却する際に利用できる空き家の譲渡所得の特例は、節税に大きく貢献する制度ですが、その要件や手続きは複雑で、変更点も多いです。
スムーズな売却に向けて、ぜひこの記事を参考にしてください。
2023年度に税制改正!空き家に関する特例変更点の概要
控除額の変更点
2023年度の税制改正により、空き家の譲渡所得の特例における控除額に重要な変更がありました。
従来は、相続人の人数に関わらず、譲渡所得から3,000万円を控除することができました。
しかし、改正後は、相続人が3人以上の場合は控除額が2,000万円に減額されます。
相続人の人数によって控除額が変わることを理解し、事前に控除額を正確に計算することが重要です。
複数人で相続する場合は、この変更点を踏まえた上で売却計画を立てる必要があります。
耐震基準と解体に関する変更点
以前は、空き家の譲渡時に耐震基準を満たしているか、もしくは譲渡までに解体工事を完了していることが条件でした。
そのため、相続人は譲渡前に費用を負担して耐震改修工事や解体工事を行う必要があり、大きな経済的負担となっていました。
しかし、2023年度の税制改正により、この条件が緩和されました。
譲渡後、譲渡年の翌年2月15日までに耐震基準を満たす改修工事の完了または解体工事の完了を証明できれば、特例を受けることができるようになりました。
譲渡後、買主が改修や解体費用を負担するケースでも特例の適用が可能になった点は大きなメリットと言えます。
手続きと必要書類の確認
空き家の譲渡所得の特例を適用するには、確定申告が必要です。
必要な書類は、譲渡所得の金額の計算に関する明細書、被相続人居住用家屋等確認書など、複数あります。
さらに、相続開始前、期間、譲渡時など、様々な条件を満たしていることを証明する書類も必要となります。
具体的には、被相続人の住民票の除票、相続人の住民票、被相続人の居住用家屋の登記事項証明書、売買契約書のコピー、耐震基準適合証明書、家屋取壊し後の閉鎖事項証明書などが求められる場合があります。
これらの書類は、税務署に提出する必要があります。
事前に必要書類をリストアップし、漏れがないように準備することが重要です。
不明な点があれば、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
空き家の譲渡所得の特例制度とは
特例制度の目的と概要
この特例制度は、増加する空き家問題の解決を目的としています。
老朽化した空き家は、防災上のリスクや景観の悪化につながるため、その有効活用を促進することが重要です。
この制度は、相続により空き家を相続した人が、それを売却する際に、譲渡所得から一定額を控除できるというものです。
これにより、売却を促進し、空き家問題の解消に貢献しようとする制度です。
適用条件の詳細
特例制度の適用には、いくつかの条件があります。
まず、相続開始直前まで被相続人が居住していたこと、昭和56年5月31日以前に建築された戸建て住宅であること、相続開始日から3年以内に譲渡すること、譲渡価格が1億円以下であることなどです。
また、譲渡する建物は、耐震基準を満たしているか、または譲渡後一定期間内に解体されている必要があります。
これらの条件をすべて満たしている必要があります。
条件を満たしていないと、特例は適用されませんので、注意が必要です。
特例適用を受けるための手続き
特例を適用するには、確定申告を行う必要があります。
確定申告書には、譲渡所得の金額の計算に関する明細書や被相続人居住用家屋等確認書などを添付する必要があります。
確認書は、市区町村役場に申請して取得します。
申請には、相続関係を証明する書類や、家屋の状況を示す書類などが必要となるため、事前に準備しておきましょう。
また、必要書類の提出期限にも注意が必要です。
期限までに必要な書類をすべて揃えて、税務署に提出しましょう。
税制改正に関するよくある質問と注意点
相続人の人数と控除額の関係
相続人の人数によって控除額が異なります。
相続人が1人または2人の場合は3,000万円の控除が受けられますが、3人以上の場合は2,000万円に減額されます。
相続人が複数いる場合は、この点を考慮して売却計画を立てる必要があります。
また、相続税の申告と譲渡所得税の申告をどのように行うかについても検討が必要です。
他の特例との併用について
この特例は、他のいくつかの特例と併用できます。
例えば、「自己の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」や「自己の居住用財産の買換え等に係る特例措置」などです。
ただし、併用できる特例とできない特例があるので、注意が必要です。
特に、相続税の取得費加算の特例とは併用できません。
どのような特例と併用できるのか、専門家に相談することをお勧めします。
申請における注意点とトラブル防止策
申請にあたっては、各条件を満たしているか、必要書類をすべて準備しているかなどを十分に確認することが重要です。
些細なミスが、特例適用を妨げる原因となる可能性があります。
また、譲渡契約書に、税制改正後の特例適用に関する事項を明記しておくことも重要です。
事前に税理士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることで、トラブルを未然に防ぎ、スムーズな手続きを進めることができます。
まとめ
2023年度の税制改正により、空き家の譲渡所得の特例制度に変更がありました。
特に、相続人の人数と控除額の関係、耐震基準と解体に関する条件の緩和は、売却を検討する上で重要なポイントです。
売却を検討する際は、これらの変更点を理解し、必要書類を漏れなく準備して、確定申告を行う必要があります。
適切な手続きを行うことで、節税効果を最大限に活かし、相続手続きを円滑に進めることが可能です。
この制度を活用して、空き家問題を解決し、相続手続きをスムーズに進めましょう。
ご自宅や相続した物件、空き家など保持しているけれど活用できていないなどのお悩みございませんか?
アーバンネットワークでは、お客様の声に寄り添った提案でスムーズに売却までお手伝いいたします。無理強いや、お客様のお気持ちに添わない金額の引き下げなどは一切行いませんので、ご安心くださいませ。
お電話でのお問い合わせは 0859-30-2468 まで、
またはお問い合わせページからもご連絡いただけます。
皆さまからのお問い合わせを心よりお待ちしております。
お問い合わせ
CONTACT
「悩みがある・困っている・売りたい、買いたい」
何でもご相談ください!