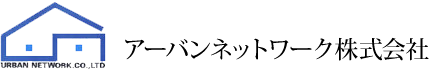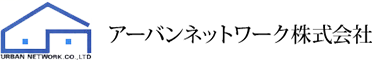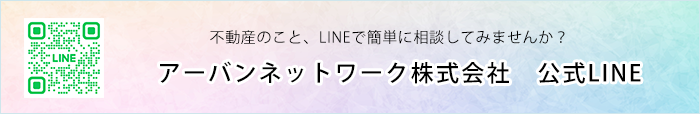ブログ
BLOG
住宅ローン控除と税制改正!住民税控除額を理解しよう
不動産コラム
2025.08.01
みなさん、こんにちは!
米子市不動産売却を行っておりますアーバンネットワーク株式会社です!
長年の経験と豊富な知識を活かし、お客様の大事な住宅の売却をサポートいたします。
ここでは、不動産に関するお役立ち情報をご紹介いたしますので、ぜひご覧ください。
住宅ローン控除は、マイホーム購入において大きなメリットとなる制度です。
しかし、その仕組みや税制改正による影響、特に所得税で控除しきれなかった場合の住民税への控除については、複雑で分かりにくいと感じている方も多いのではないでしょうか。
今回は、住宅ローン控除の基礎知識から、税制改正による変更点、住民税への控除について、具体的に解説します。
住宅ローン控除は、正式名称を「住宅借入金等特別控除」といい、住宅ローンを利用して住宅を取得・新築・増改築した際に、一定の条件を満たせば、年末時点の住宅ローン残高の一定割合を所得税から控除できる制度です。
住宅ローン減税と呼ばれることもあります。
控除期間は最長13年(既存住宅の増改築は最長10年)で、2025年12月31日までに住宅に入居した分までが対象です。
控除の対象となる住宅には、いくつかの条件があります。
まず、住宅ローンを借り入れた本人が居住する住宅である必要があります。
また、新築住宅だけでなく、中古住宅の購入やリフォームも対象となりますが、新築・中古・リフォームの別や住宅の環境性能によって、控除期間や借入限度額が異なります。
新築住宅については、2024年1月1日以降に建築確認を受けた住宅、あるいは2025年6月30日以降に建築された住宅は、省エネ基準を満たさなければ控除の対象外となる点に注意が必要です。
住宅ローン控除を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
共通の条件として、住宅ローンの返済期間が10年以上であること、ローン契約者本人が居住していること、引渡し・工事完了から6カ月以内に入居していることなどが挙げられます。
また、合計所得金額や床面積に関する制限も存在します。
新築住宅の場合は、前述の通り省エネ基準の適合が求められる場合もあります。
中古住宅やリフォームの場合は、建築年数や耐震基準、リフォーム費用など、さらに具体的な条件が設定されています。
詳細な条件については、国税庁や各自治体のホームページなどを確認することをお勧めします。
2024年以降の税制改正では、住宅ローン控除の適用ルールに変更がありました。
特に新築住宅については、省エネ基準の厳格化や借入限度額の変更が大きなポイントです。
省エネ基準を満たさない新築住宅は、原則として控除の対象外となりました。
ただし、一定の条件を満たすことで特例的に控除を受けることができる場合があります。
また、住宅の種類によって借入限度額が引き下げられました。
ただし、子育て世帯や若者夫婦世帯については、一定の期間、改正前の限度額が適用されるケースもあります。
所得税から控除できる住宅ローン控除額が、その年の所得税額を上回った場合、所得税から控除しきれない金額が発生します。
この超過分については、一定の条件を満たせば、翌年の住民税から控除を受けることができます。
これは、所得税と住民税の両方を活用して税負担を軽減できる仕組みです。
住民税からの控除額には上限があります。
上限額は、所得税の課税所得金額の5%(上限9万7,500円)または、所得税で控除しきれなかった金額のいずれか少ない方となります。
ただし、住宅取得にかかった消費税の税率が8%または10%の場合は、上限が7%(上限13万6,500円)となる場合があります。
控除額の計算方法は、所得税で控除しきれなかった金額を、住民税の控除上限額と比較して、少ない方を控除額とします。
住民税からの住宅ローン控除を受けるために、特別な手続きは必要ありません。
所得税の確定申告または年末調整で住宅ローン控除の手続きを行うことで、必要な情報は税務署から市区町村に共有されます。
そのため、住民税の控除を受けるために、市区町村に改めて申告する必要はありません。
住宅ローン控除の手続きは、初年度は確定申告、2年目以降は会社員の場合は年末調整、個人事業主や自営業者の場合は確定申告で行います。
確定申告や年末調整では、住宅ローン控除を受けるための必要書類を提出する必要があります。
これらの書類には、住宅ローン残高証明書、住宅の登記事項証明書、契約書などがあります。
ふるさと納税と住宅ローン控除は併用できますが、控除額の上限に注意が必要です。
ふるさと納税は所得税と住民税の両方から控除されますが、控除できる金額には上限があり、ふるさと納税による控除と住宅ローン控除を合わせた控除額が上限を超えることはありません。
特に確定申告でふるさと納税の手続きを行う場合は、所得税からの控除額が減るため、住民税からの控除額も影響を受ける可能性があります。
住宅ローン控除は、他の税制優遇制度と併用できる場合があります。
例えば、iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金は所得控除として扱われ、住宅ローン控除とは控除の仕方が異なりますが、併用することでより大きな節税効果が期待できます。
ただし、それぞれの控除制度には条件や制限があるため、併用する場合には事前に確認が必要です。
本記事では、住宅ローン控除、特に所得税で控除しきれなかった部分の住民税への控除について解説しました。
2024年以降の税制改正により、省エネ基準や借入限度額に関するルールが変更されているため、最新の情報を確認することが重要です。
所得税と住民税の両方から控除を受けることで、税負担を軽減できる可能性があります。
ただし、ふるさと納税や他の控除制度との併用、控除額の上限など、注意すべき点もいくつかあります。
マイホーム購入を検討している方は、これらの点を理解し、賢く住宅ローン控除を活用しましょう。
ご自宅や相続した物件、空き家など保持しているけれど活用できていないなどのお悩みございませんか?
アーバンネットワークでは、お客様の声に寄り添った提案でスムーズに売却までお手伝いいたします。無理強いや、お客様のお気持ちに添わない金額の引き下げなどは一切行いませんので、ご安心くださいませ。
お電話でのお問い合わせは 0859-30-2468 まで、
またはお問い合わせページからもご連絡いただけます。
皆さまからのお問い合わせを心よりお待ちしております。
米子市不動産売却を行っておりますアーバンネットワーク株式会社です!
長年の経験と豊富な知識を活かし、お客様の大事な住宅の売却をサポートいたします。
ここでは、不動産に関するお役立ち情報をご紹介いたしますので、ぜひご覧ください。
住宅ローン控除は、マイホーム購入において大きなメリットとなる制度です。
しかし、その仕組みや税制改正による影響、特に所得税で控除しきれなかった場合の住民税への控除については、複雑で分かりにくいと感じている方も多いのではないでしょうか。
今回は、住宅ローン控除の基礎知識から、税制改正による変更点、住民税への控除について、具体的に解説します。
住宅ローン控除の基礎知識
住宅ローン控除とは何か
住宅ローン控除は、正式名称を「住宅借入金等特別控除」といい、住宅ローンを利用して住宅を取得・新築・増改築した際に、一定の条件を満たせば、年末時点の住宅ローン残高の一定割合を所得税から控除できる制度です。
住宅ローン減税と呼ばれることもあります。
控除期間は最長13年(既存住宅の増改築は最長10年)で、2025年12月31日までに住宅に入居した分までが対象です。
控除の対象となる住宅
控除の対象となる住宅には、いくつかの条件があります。
まず、住宅ローンを借り入れた本人が居住する住宅である必要があります。
また、新築住宅だけでなく、中古住宅の購入やリフォームも対象となりますが、新築・中古・リフォームの別や住宅の環境性能によって、控除期間や借入限度額が異なります。
新築住宅については、2024年1月1日以降に建築確認を受けた住宅、あるいは2025年6月30日以降に建築された住宅は、省エネ基準を満たさなければ控除の対象外となる点に注意が必要です。
控除を受けるための条件
住宅ローン控除を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
共通の条件として、住宅ローンの返済期間が10年以上であること、ローン契約者本人が居住していること、引渡し・工事完了から6カ月以内に入居していることなどが挙げられます。
また、合計所得金額や床面積に関する制限も存在します。
新築住宅の場合は、前述の通り省エネ基準の適合が求められる場合もあります。
中古住宅やリフォームの場合は、建築年数や耐震基準、リフォーム費用など、さらに具体的な条件が設定されています。
詳細な条件については、国税庁や各自治体のホームページなどを確認することをお勧めします。
住民税への影響
2024年以降の税制改正による変更点
2024年以降の税制改正では、住宅ローン控除の適用ルールに変更がありました。
特に新築住宅については、省エネ基準の厳格化や借入限度額の変更が大きなポイントです。
省エネ基準を満たさない新築住宅は、原則として控除の対象外となりました。
ただし、一定の条件を満たすことで特例的に控除を受けることができる場合があります。
また、住宅の種類によって借入限度額が引き下げられました。
ただし、子育て世帯や若者夫婦世帯については、一定の期間、改正前の限度額が適用されるケースもあります。
所得税控除しきれなかった場合の住民税控除
所得税から控除できる住宅ローン控除額が、その年の所得税額を上回った場合、所得税から控除しきれない金額が発生します。
この超過分については、一定の条件を満たせば、翌年の住民税から控除を受けることができます。
これは、所得税と住民税の両方を活用して税負担を軽減できる仕組みです。
住民税控除の上限額と計算方法
住民税からの控除額には上限があります。
上限額は、所得税の課税所得金額の5%(上限9万7,500円)または、所得税で控除しきれなかった金額のいずれか少ない方となります。
ただし、住宅取得にかかった消費税の税率が8%または10%の場合は、上限が7%(上限13万6,500円)となる場合があります。
控除額の計算方法は、所得税で控除しきれなかった金額を、住民税の控除上限額と比較して、少ない方を控除額とします。
住民税控除の手続き
住民税からの住宅ローン控除を受けるために、特別な手続きは必要ありません。
所得税の確定申告または年末調整で住宅ローン控除の手続きを行うことで、必要な情報は税務署から市区町村に共有されます。
そのため、住民税の控除を受けるために、市区町村に改めて申告する必要はありません。
住宅ローン控除の活用と注意点
確定申告と年末調整の手続き
住宅ローン控除の手続きは、初年度は確定申告、2年目以降は会社員の場合は年末調整、個人事業主や自営業者の場合は確定申告で行います。
確定申告や年末調整では、住宅ローン控除を受けるための必要書類を提出する必要があります。
これらの書類には、住宅ローン残高証明書、住宅の登記事項証明書、契約書などがあります。
ふるさと納税との併用について
ふるさと納税と住宅ローン控除は併用できますが、控除額の上限に注意が必要です。
ふるさと納税は所得税と住民税の両方から控除されますが、控除できる金額には上限があり、ふるさと納税による控除と住宅ローン控除を合わせた控除額が上限を超えることはありません。
特に確定申告でふるさと納税の手続きを行う場合は、所得税からの控除額が減るため、住民税からの控除額も影響を受ける可能性があります。
その他控除との関係
住宅ローン控除は、他の税制優遇制度と併用できる場合があります。
例えば、iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金は所得控除として扱われ、住宅ローン控除とは控除の仕方が異なりますが、併用することでより大きな節税効果が期待できます。
ただし、それぞれの控除制度には条件や制限があるため、併用する場合には事前に確認が必要です。
まとめ
本記事では、住宅ローン控除、特に所得税で控除しきれなかった部分の住民税への控除について解説しました。
2024年以降の税制改正により、省エネ基準や借入限度額に関するルールが変更されているため、最新の情報を確認することが重要です。
所得税と住民税の両方から控除を受けることで、税負担を軽減できる可能性があります。
ただし、ふるさと納税や他の控除制度との併用、控除額の上限など、注意すべき点もいくつかあります。
マイホーム購入を検討している方は、これらの点を理解し、賢く住宅ローン控除を活用しましょう。
ご自宅や相続した物件、空き家など保持しているけれど活用できていないなどのお悩みございませんか?
アーバンネットワークでは、お客様の声に寄り添った提案でスムーズに売却までお手伝いいたします。無理強いや、お客様のお気持ちに添わない金額の引き下げなどは一切行いませんので、ご安心くださいませ。
お電話でのお問い合わせは 0859-30-2468 まで、
またはお問い合わせページからもご連絡いただけます。
皆さまからのお問い合わせを心よりお待ちしております。
お問い合わせ
CONTACT
「悩みがある・困っている・売りたい、買いたい」
何でもご相談ください!