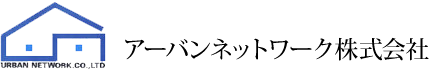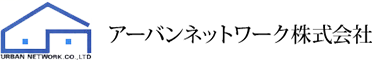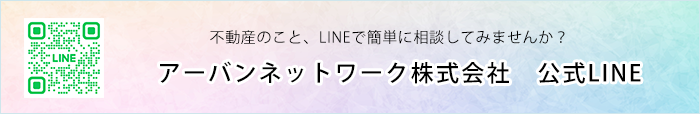ブログ
BLOG
2019.02.27
不動産コラム
相続をした空き家をもっていて、売却を考えている方はいらっしゃいませんか?
実は2016年の4月から、相続した空き家を売却した場合に、一定の条件を満たしていると、3000万円の特別控除の特例を受けることができるかもしれません。
今回は、この制度を受ける条件などの詳細について見ていきます。
□制度の概要
3000万円の控除の特例は正式には「空き家の発生を抑制するための特例措置」といわれています。
この制度を利用すると、不動産を売った際の税金が非課税となり、より多くのお金が手元に残ることでしょう。
□譲渡所得とは
譲渡所得は特別控除の恩恵を受けられるかどうかを知る際にとても重要です。
譲渡所得というものは、所得税や住民税を課せられるものだからです。
譲渡所得の求め方を見てみましょう。
*譲渡所得の求め方
ご紹介している特例を適用した場合は、
譲渡所得 = 譲渡収入金額 - (取得費 ₊ 譲渡費用) - 特別控除3000万円
条件を満たし、この特例を受けられる対象であるなら、最終的に3000万円引いた金額に税金がかかるのです。
つまり、ほとんどの場合譲渡所得は0以下になるため、課税されないのです。
□特例を受けるため用条件
3000万円の特例措置を受けるには、いくつかの条件を満たす必要があります。
以下はその一般的な条件になります。
*適用期間について
住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する必要があります。
しかし、これについては変更が行われ、2019年12月31日までとされていた適用期限が2023年12月31日までに延長されます。
期間は変わりましたが、条件についてはこれまで通りな点に注意しましょう。
*相続した家屋について
特例対象の家屋は以下の通りです。
・相続が開始する直前まで被相続人が生活をしていた
・相続が開始する直前まで被被相続人以外が生活していない
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
・相続してから売却までに、事業用、貸付け用、居住用に使用していないこと
*売却時について
不動産の譲渡・売却をする際の条件もございます。
・譲渡価額が1億円以下
・当該家屋が現行の耐震基準に適合するも
のであること
□まとめ
相続された不動産を売却する際に、3000万円の控除が受けられ非課税となる制度について見てきました。
相続した不動産が空き家のままになっている場合は、売却について検討してみてもよいかもしれませんね。
売却の際は今回ご紹介した特例に条件が当てはまるかご参考にしてみてください。
2019.02.23
不動産コラム
不動産などの資産の相続をスムーズに行うためには、生前準備が欠かせません。
生前準備を行っていないと、相続税の申告にあたふたすることになったり、相続対策に出遅れてしまうことになります。
そこで今回は、不動産を相続する際に必要な生前準備について見ていきます。
□財産の把握
相続を受けるにあたって知っておかなければならないことは、相続を行うと、現金や不動産など活用できる資産の他にも負債やローンも相続されてしまうということです。
相続を行う際は、不動産などのことだけでなく、他にもローンや借金がないかどうかよく確認をしておきましょう。
□相続人を誰にするか
ご両親など相続をする側の方が亡くなってから相続人を誰にするか選ぶ場合、相続の割合などの話がまとまりにくくなってしまいます。
しっかりと生前準備で誰がどのくらいの割合の財産を相続するか確定させておきましょう。
具体的な準備としては、家族関係図を作成し、さらに相続人を確定させるために、相続される方の「出生から死亡までの連続した戸籍謄本等」を市区町村の役場で所得しておきましょう。
□遺言書の作成
不動産などの資産を相続するための生前準備として最も有名なのが遺言書の作成です。
意思がきちんと示すことができる生前のうちに、きちんと相続人を書いた遺言書を作成しておくことで、遺産争いによって家族の仲が悪くなってしまうことが少なくなります。
*遺言書の作成
遺言書はきちんとした手順に沿って書かれていなければ、無効になることも考えられます。
遺言書を書く際に確認しておかなくてはならないのは、公正証書遺言の作成方法、遺言書の作成費用、遺言執行者の指定などについてです。
以上をしっかりと確認して遺言書を作成しましょう。
□税金の対策
不動産の相続にあたっては、税金の対策も重要です。
遺産のほとんどを不動産が占めている場合、納税をしようにもできないことが考えられます。
そのため、不動産が不要なのであれば売却したりして、現金化するのも一つの手です。
そして、税金対策には生前贈与という手もあります。
*生前贈与とは
生前贈与はその名の通り、生前に相続することですが、その最大のメリットは節税対策になるということです。
平成25年度から税法が改正され、相続税が増税されたことから、生前に相続してこの増税を回避しようという方が増えてきています。
□まとめ
不動産相続に対する生前準備には、さまざまなものがあるということが分かりました。
どちらにせよ、生前準備を行っておくことで、その後に家族がバラバラになってしまうという状況を回避することができるかもしれません。
ぜひとも相続の生前準備を検討してみてください。
2019.02.19
不動産コラム
ご両親が亡くなってしまい、実家が空き家として残ってしまっている場合、売却を検討される方も多いかと思います。
というのも、やはり空き家として放置しておくと、それだけ税金もかかりますし、維持管理の責任も生じるからです。
しかし、思い入れのある実家を売却するとなると、適当に行うことはできませんよね。
そこで今回は、実家を売却する際の手順について丁寧に見ていきましょう。
□相続登記を行う
すでにご両親が他界されている場合、最初に相続登記を済ませておく必要があります。
これをやっておかないと、実家を売却する際に、権利関係のトラブルが生じてしまうことになりかねません。
相続登記は各地の法務局で行います。
□査定を行う
相続登記を行った次の手順は、査定してもらいます。
査定を行う際に、不動産会社を回って、どこが一番高く売却できるかということを考えることも面倒かつ時間がかかってしまいます。
そのため余裕を持って査定にのぞむことをおすすめします。
一括査定ではなく、複数の不動産会社から査定を受けて自分が心から依頼したいと思えるところに決めましょう。
□仲介業者と契約を行う
査定を行った後で、心に決めた不動産会社があれば、そこの会社に決めて契約を行いましょう。
□売り出される
仲介業者と契約ができると、仲介業者はいよいよ売却を開始します。
すべての事務的な手続きなどはすべて選んだ会社がやってもらえるので任せましょう。
□内見案内
購入を希望する人が現れると、希望者に対して内見の案内をします。
内見に関しても、不動産会社に任せることができますが、付き添いを希望すれば一緒に内見を回ることができます。
□条件の交渉
内見の案内が終わり、そのまま購入希望の方がいらっしゃる場合、価格などの交渉に入ります。
基本的に値下げ交渉が行われるので、ある程度の値下げには対応できるよう準備ができているとスムーズに交渉ができるでしょう。
□売買契約
価格面やその他の条件で折り合いがつくと、売買の契約が結ばれます。
□物件引き渡しと登記
契約が終わると、いよいよ最後の手順で、実際にその物件を引き渡すことになります。
基本的に不動産会社などが準備してくれますが、登記などの変更も忘れないようにしましょう。
□まとめ
以上が基本的な実家を売却する際の手順となります。
実家についてできるだけ高く売れるように部屋の掃除などを事前に行ってから売却しましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
2019.02.15
不動産コラム
ご両親などが所有していた土地を相続することになったときに考えなければならないのが土地をどのように活用するかです。
しかし、急に相続された土地の活用法を考えろといわれても、よくわからないという方がほとんどだと思います。
そこで今回は、相続された土地を有効活用する方法をいくつかご紹介します。
□土地の有効活用方法
*賃貸アパート・マンション経営
収益性で考えたときに、最も高い収益性があるのが賃貸アパート・マンション経営です。
一方で空室などが発生すると、経済的なリスクになる場合もあります。
自身で運営する自信がない方は、賃貸アパート・マンション経営の管理会社に委託することで、手間をかけずにアパート・マンションを経営することが可能です。
ただ、これらの場合はまとまった初期費用が必要であることがデメリットでしょう。
*戸建賃貸
賃貸で戸建てを借りたいファミリー層にとって、戸建ての賃貸物件というのは貴重です。
しかし、その数はあまり多くなく、需要のある土地で運用できれば安定して収益を得ることが可能です。
戸建賃貸は、マンションやアパートに比べても建築コストを抑えることができ、さらに、手放したくなった時は売却しやすいということも魅力です。
しかしこちらも初期費用はある程度かかると考えておいた方がよさそうです。
*駐車場
駐車場は相続された土地の有効活用方法として比較的手軽な例です。
駐車場を運営するには、月極駐車場かコインパーキングかの違いがあります。
月極駐車場の場合、管理会社などに経営を委託することが可能ですが、自ら運営することが一般的です。
駐車場は初期投資が少なく、将来他の用途にその土地を使いたい考えたときに、すぐに転用できることも駐車場のメリットです。
コインパーキングの場合、大手の専門業者に依頼をして賃料を得るというスタイルになります。
運営自体を依頼するので、管理などのことについて考える必要はなくなります。
ただ、これらのような駐車場にするには、車を停めたい人が多くいる場所である必要があります。
例えば駅やショッピングモールに近いといったような場合だと、駐車場として活用しやすいでしょう。
□まとめ
ここまで、相続された土地の活用方法についてご紹介しました。
土地の有効活用方法には、マンションやアパートの運営、戸建ての賃貸、駐車場にするといったものがあることがわかりました。
ご自身の土地柄に合った有効活用方法をぜひお試しください。
2019.02.11
不動産コラム
ご両親が亡くなってしまい、空き家が資産として残っている場合、それを相続するかどうかは迷ってしまいますよね。
それはやはり空き家を維持管理することはコストがかかるからです。
ではとりあえず相続だけして、放置しておくことはどうなのでしょうか。
今回は、空き家を放置することのデメリットをご紹介します。
□資産としての価値の低下
土地のように時間の経過とともに価値が変化しにくいものと違い、家というのは必ず老朽化していきます。
ましてや、住む人がいない状態で放置をしておくと、余計に老朽化が進んでしまいます。
のちに家を売却しようと考えた時、老朽化してしまっているので、その価値はかなり下がってしまいます。
□近隣の住宅とのトラブル
空き家の老朽化が進むと、極端な例では倒壊などの危険性があります。
そうなった場合に他の家を巻き込んでしまうと、もちろん管理責任が問われることになります。
さらに、倒壊とまではいかなくても、突風などの災害で、家の一部の部分が他人の家に飛んで行ってしまった場合でも、損害の賠償が請求されたりして思わぬトラブルの原因になってしまう可能性があります。
□税金のデメリット
空き家であっても固定資産税などの税金は納める必要があります。
さらに、特定空き家というものに指定されてしまうと、税金面での優遇措置は一切なくなり、通常の6倍程度の税金が課されてしまいます。
特定空き家とは、植物が生い茂っていたり、人が長年出入りしてないような空き家で、不法侵入などによるたまり場になる恐れのある空き家のことです。
□放置によるデメリットをなくすには
空き家を放置することはさまざまなデメリットがあることがわかりました。
それではこのデメリットをなくすには、どのような手が考えられるのでしょうか。
*相続を放棄する
相続を放棄すると、空き家などの維持管理コストのかかる資産を相続する必要がなくなります。
一方で、相続放棄はすべての資産に対して相続権を放棄することになるので、他に資産があっても受け取れなくなってしまいます。
*空き家を売却する
長年放置してしまうのならば、資産価値のあるうちに売却したほうが、メリットは大きいです。
空き家を高く売りたい場合は、綺麗に掃除をして、照明を変えるだけでも印象が変わり、不動産会社にも高値で評価される可能性が高まります。
□まとめ
空き家を放置することにはやはりデメリットがたくさんあります。
そのデメリットをなくすには、相続を放棄することや早めに売却をするという手が考えられます。
どちらの方がご自身にとって利点が多いかも考えてくださいね。
2019.02.07
不動産コラム
ご両親が亡くなった場合などで、空き家の相続権を得た場合に、悩みどころなのが本当にそれを相続するかどうかです。
というのも、空き家などに関しては維持管理コストが高く、相続した場合は周りの家などにも迷惑をかけないようにする責任も生じてしまいます。
そこで考えられることが空き家を売却するという手です。
空き家を売却すると、管理責任などもなくなりますし、資産にもなり得ます。
そこで今回は、空き家をなるべく高く売るにはどのようにすればよいのかということについてお伝えしていきます。
□空き家を高く売るには
空き家を高く売るには、いくつかのポイントがあります。
それらを見ていきましょう。
*不動産会社の選び方
不動産会社によって、空き家を売る際の値段は大幅に変わってきます。
それは、不動産会社によってマンションが得意の会社だったり、賃貸物件だけを取り扱っていたり、会社はそれぞれ差別化していて得意な分野が違うためです。
売却をお考えの場合、土地や中古一戸建て・マンションを扱う不動産会社にするとよいでしょう。
*掃除について
空き家を高く売るには、その空き家が魅力的であればあるほど高く売れる可能性が高まります。
空き家を魅力的に見せるにはやはり掃除することが一番手っ取り早いです。
しかし、長年の汚れなどで、掃除が簡単でない場合などもあるかと思います。
そんなときは、ハウスクリーニングを業者に依頼するのも一つの手です。
費用はやはりかかってしまいますが、それでも業者による掃除によって不動産会社が高値で空き家を買い取ってくれるようになる可能性はあります。
掃除にかかる費用と買い取り価格を比較して、検討してください。
*部屋を明るく見せる
部屋の印象を大きく変えるものとして照明器具があります。
部屋をどれだけ綺麗にしても照明がうす暗ければ暗い印象になってしまいます。
逆に、照明を明るくするだけでそれなりに明るい印象を与えることができます。
照明を変えることは簡単にできるので、空き家を売る際は照明を明るいものに変えてみてはいかがでしょうか。
□空き家売却の際にかかる税金について
空き家を売却する際は、かかる税金についても考慮しておかなければなりません。
これを知らないと、手にした金額に落胆してしまうこともあります。
空き家を売却する際にかかる税金は譲渡所得税です。
譲渡所得税は、譲渡益に対して発生します。
□まとめ
空き家を高く売るには不動産選びから、部屋の掃除、照明の変更ということをすると良いでしょう。
また、空き家を売る際は税金などについても考えておかなくてはならないので注意しておきましょう。
2019.02.04
不動産コラム
先祖代々から続く土地を受け継ぐということは、どのようなことなのでしょうか。
資産が増えるため、よいことと考えられている方が多くいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は不動産の大きさに関係なく、先祖からの土地を相続する場合には、どのようなメリットとデメリットがあるのかについてご紹介します。
□不動産相続のメリットとは
まずはメリットから考えましょう。
土地を相続するという事は資産を受け継ぐという事になります。
資産が増えるわけですから、その点はメリットと考えてよいでしょう。
ただし、その土地が価値のある土地である場合の話に限ります。
例えば町から大変離れた人気の少ない土地を受け継いで、そこに賃貸マンションやアパートを建てても需要は果たしてあるのでしょうか。
さらにそれを売ろうとしてもなかなか買い手がつかない可能性があります。
昔日本では1億総中流と言われていた時代がありました。
その時代には、土地は一定の価値がある場合が多いものでした。
しかし二極化が進む現代では、価値のある土地とそうでない土地が大きく分かれてきており、将来的にはそれがさらに加速化していくことが考えられます。
そのため価値の低い土地を受け継いでも、資産ではなく負債になってしまう恐れもあるのです。
受け継ぐ予定の土地や家が、どのような立地であるのかを考える必要があります。
土地や建物を受け継ぐことができたからと言って、むやみやたらに喜べる時代ではなくなっています。
□不動産相続のデメリットとは
では、今度はデメリットを考えてみましょう。
土地や家屋を受け継ぐ場合には、現金と違い相続が難しいことが挙げられます。
現金はうまく兄弟間で分けることが可能だが、土地や家屋の場合には、必ずと言ってよいほど、もめごとが発生します。
それはうまく均等に分けられないことに原因があるのです。
そのようなトラブルに巻き込まれた場合は、相当な時間を取られてしまう可能性もあり、兄弟間の仲が悪くなることもあり得ます。
そのような状態になった時には、慎重に対応するべきです。
そして可能な限りもめごとは避けたいものですね。
□最後に
ここまで、不動産相続のメリット・デメリットについてご紹介しました。
今の時代では、不動産が必ず価値をもたらしてくれるもととはなり得ないことをご理解いただけたでしょうか。
また、兄弟間で起こりやすい相続トラブルについてもしっかり話し合いをすることで解消してくださいね。
2019.01.31
不動産コラム
両親が他界すると親が所有していた不動産を相続するケースは比較的多くあり、税金対策が必要になってくることが珍しくありません。
土地や一戸建て住宅、マンションなどを後継するのは良いけれども、税金を納めなければならないとなれば悩みが膨らむ人も多いのではないでしょうか。
一般的に、不動産の相続には3,000万円特別控除があるので必ずしも相続税を納めなければならないわけではありません。
そこで、今回は不動産相続に関する税金対策についてご紹介します。
□3,000万円の特別控除とは
まず、対象となる不動産の評価額を調査することが必要です。
評価額が3,300万円の場合には3,000万円までの特別控除がありますので、実質3,000万円までは非課税という形になります。
問題は、3,000万円を超える部分で、300万円については課税の対象となるので納める義務が生じることになるのです。
但し、3,000万円の特別控除には例外も認められており、相続する人数1名に対して600万円の控除が適用される仕組みがあります。
例えば、奥さんと子供2名が両親が残した遺産を後継することになった時には、600万円×3名=1,800万円が非課税となります。
これに特別控除額の3,000万円が加算されることになるので、合計4,800万円までは非課税となり、税金対策としての有効性が高くなるわけです。
□さらに税金対策をするためには
ここで重要になるのが、評価額が正しいものであるのか、それとも間違っている金額になっているのかということです。
評価額が3,300万円と言われても、実際の金額が5,000万円の場合には3人で引き継いだとしても最高4,800万円までしか非課税になりませんので、残りの200万円分は課税の対象になってしまいます。
評価額をいかに正確に導き出すのかも税金対策に必要な部分ですから、鑑定をお願いする専門家を選ぶ時には過去の実績がどの程度ある人なのかを調べておくことも大切です。
ちなみに、不動産は必ずしも子供などが引き継ぐわけでなく、旦那さんが他界した時には配偶者である奥さんが遺産を後継するケースもゼロではありません。
配偶者が遺産を引き継ぐ時には3,000万円の特例ではなく、1億6,000万円まで非課税になるので、一旦配偶者が遺産を引き継ぐことも税金対策に有効なケースがあります。
但し、注意をしなければならないことは、配偶者が3年以内に他界した時には子供達の課税額は多くなるという点です。
また、価値が高い不動産を相続した時など、1億円などの金額の物件はかなりの税金を納めなければなりませんので、売却を考えなければならないケースもあります。
□最後に
ここまで、不動産相続の税金対策についてご紹介しました。
ご家庭の事情に合わせて、適切な税金対策をして相続をしてくださいね。
2019.01.27
不動産コラム
不動産の相続を考えているならば、名義変更をしなければ自分のものになりません。
その手続は自分でもできますし、専門家である司法書士に任せることもできます。
どの方法で行うにしても、必要書類は揃えることが大切です。
必要書類と言われるものは、具体的に何があるかについてご紹介します。
□被相続人に関する必要書類
不動産を受け継ぐというときには、これまでその物件の持ち主であった被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍と故人の生まれたときから亡くなるときまで遡ることができる書類を取り寄せましょう。
これは遠い場所にある役所に請求しなければいけない場合、手間がかかります。
それから、不動産の登記簿上の住所と本籍地が書かれている住民票の除票あるいは戸籍の附票も用意しなければいけません。
次に、これまで固定資産税の支払いを行うために使われてきた固定資産評価証明書も取得しておくべきでしょう。
しかし、法務局で納税通知書があれば受け付けてくれるところもあります。
□相続人に関する必要書類
新しい持ち主となる相続人については、戸籍謄本と住民票を用意します。
戸籍謄本については法定相続人全員のものが必要で、住民票は名義人となる人だけで大丈夫です。場合によっては遺産分割協議書も用意しておきます。
名義変更をするにあたっては、戸籍謄本や除籍謄本にかかれている人間関係をわかりやすく図にした相続関係説明図は自分で作成しておかなければいけません。
自作ということで、どういうふうに作ればいいのか分からないかもしれません。
しかし難しいことを要求されているわけではなく、よくある家系図と同じで罫線を使って誰と誰が夫婦や親子なのかを書いておくだけです。
関係する人の続柄や住所、生年月日などをそばに書いておきます。
この図があることで提出した戸籍謄本の原本などがなくても、法務局は関係性を把握できます。
あとは状況によって遺言書や、必要書類が揃わないときの不在籍証明書、不在住証明書、登記済権利証などを用意しておきます。
また、手続きを司法書士に任せたいときは、そのことを新しい名義人になる人の名前で委任するということを書いた委任状も必要になります。
それらの必要書類を揃えたら名義変更の手続きができるわけですが、最後に登記申請書も作成しなければいけません。
登記申請書はインターネットから各ライティングソフトで印刷ができるテンプレートが公開されています。
ダウンロードをして印刷し、必要事項を記入してください。
名義変更をするには手数料となる登録免許税も納めることになります。
収入印紙を購入して登記申請書に貼り付けてください。
□最後に
ここまで、不動産の名義変更のために必要な書類についてご紹介しました。
必要な書類がかなり多く、一つでも欠けていると手続きができない可能性があります。
そのため、自分でできそうにないと感じる方は専門家に依頼することがおすすめです。
2019.01.23
不動産コラム
両親や祖父母、親戚から財産を相続するとき、主がいなくなった空き家が含まれていると扱いに困ります。
今は別の場所で生活しているならば、仕事をやめたり子供に転校させてまで移り住むことは大変です。
それに売るとしても田舎だとあまり高値では売れません。
そこで、空き家を相続するメリットについてご紹介します。
□リフォーム・リノベーションによる需要の増加
ひとつは収入を生む資産となる可能性があることです。
古い家ならばリフォームやリノベーションをして、誰かに貸してしまうということもできます。
工事費用と相続税の負担はありますが、うまく賃貸経営ができれば給料とは別に家賃収入が継続して入るかもしれません。
もし入居者が入らなくなっても、その時に売却をすればいいのです。
リフォーム・リノベーションをして建物の状態をよくすれば、買い手が見つかる可能性も高まります。
それに賃貸として貸し出した時、空き室になったとしても、そこにもメリットがあります。
そのメリットとは、賃貸経営で生じた損失は給与所得がある人ならば、そちらと合わせて計算することができるからです。
それを損益通算と言いますが、赤字がある分だけ給与所得にかかっていた所得税が減額されて還付金が戻ってきます。
そのためには確定申告が必要ですが、必要な書類を用意することはあまり難しくありません。
□駐車場として土地活用する
もし賃貸物件としての需要がないのであれば、更地にして駐車場にするという選択肢もあります。駐車場にしてしまえば、今問題になっている空き家の心配もなく、賃料が入ってきます。
□退職後のセカンドライフのために
それから今は住む予定がなくても、将来的にその家で住むという選択肢もあります。
会社勤めをしている間は都会で暮らし、定年退職をして子どもたちも独立したならば、田舎でのんびりと暮らすという人は結構多いのです。
それにずっと家を購入することなく、賃貸暮らしをしている人が、老後に落ち着いて余生を過ごせる家として使うこともあります。
子供の頃住んでいた家、青春時代を過ごした場所であれば、思い入れもあることでしょう。
そこに戻れるということに喜びを感じることは、不思議ではありません。
空き家を持ち続けるならば、定期的に空気の入れ替えや固定資産税の支払いなどをしなければいけませんが、拠り所になる場所があると生活に張り合いが出てきます。
□最後に
ここまで、空き家を相続するメリットについてご紹介しました。
相続が発生するとき、そのまま受け継ぐか、それとも相続放棄をするべきかは、3ヶ月以内に決めなければいけません。
いろいろとリスクも多いとされる空き家にはこれらのメリットがあることを踏まえて、最善の選択をしましょう。
お問い合わせ
CONTACT
「悩みがある・困っている・売りたい、買いたい」
何でもご相談ください!