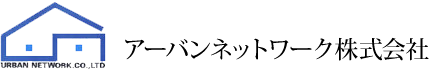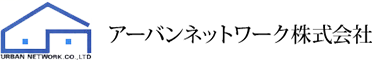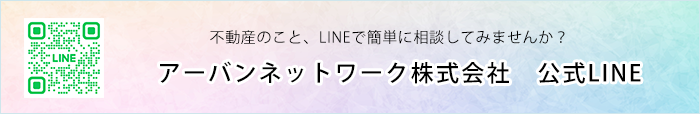ブログ
BLOG
2022.12.09
不動産コラム
最近は、空き家に関する社会問題が深刻化しています。
近隣住民の生活に影響を与える空き家ですが、今後も増加していくだろうと予測されています。
空き家は早めに売却することがおすすめですが、多大な解体費用によって放置される方も多くいらっしゃいます。
今回は、空き家解体に利用できる補助金制度について紹介します。
□空き家の解体にかかる費用とは?
空き家の解体費用は住宅の構造や使用されている素材によって大きく異なります。
一般的な空き家の解体費用を以下の3種類の住宅に分けて紹介します。
・木造建築
・軽量鉄骨造建築
・RC造建築
まずは、木造建築の空き家に関する解体費用についてです。
広さが20坪程度であれば、70万円から120万円はかかると見込むと良いでしょう。
また、30坪であれば105万円から180万円、40坪は140万円から240万円程度かかります。
次に、軽量鉄骨造建築の解体費用です。
同様に、20坪ほどの空き家であれば80万円から140万円、30坪だと120万円から210万円はかかるでしょう。
40坪程度の広さであれば、160万円から280万円まで跳ね上がるケースもあります。
そして、RC造建築の解体費用です。
RC造とは、いわゆる鉄筋コンクリート造の住宅です。
20坪の広さでは、110万円から160万円、30坪だと165万円から240万円はかかるでしょう。
また、40坪の広さでは220万円から320万円程度かかることを理解しておくと安心です。
このように、空き家を解体することで、費用がかさむのはデメリットであると言えます。
しかし、空き家を解体することで、周辺の住民に悪影響を与えずに済むことがメリットとして挙げられます。
例えば、放火犯による空き家への放火によって、近隣住民が被害を受けた際は、空き家の所有者が損害賠償を支払うケースがあります。
したがって、今後のトラブルを考慮しても空き家を放置することはおすすめしません。
□空き家解体に利用できる補助金制度とは?
空き家の解体費用には莫大な費用がかかってしまいますが、その費用負担を軽減できる制度があります。
地域や自治体によって呼び名は異なりますが、主な4つの補助金制度について紹介します。
*危険廃屋解体補助金
これは、放置していると危険だと判断された空き家の解体に適用できる補助金制度です。
危険廃屋解体補助金は周辺住民の安全を考慮して、空き家の解体を促進させるために発案されたものです。
*空き家解体補助金
空き家解体補助金とは長期間使用されていない空き家であると、自治体から認められた場合に利用できる解体補助金です。
*建て替え工事補助金
建て替え工事補助金とは、耐震性に欠けている空き家の補強工事や解体工事に対してかけられる補助金です。
この補助金を適用するにあたって、事前に耐震診断を行う必要があります。
□補助金制度を利用する際の注意点とは?
空き家の解体に対して適用できる補助金制度ですが、適用する際に注意しておくべきポイントがあります。
これらの注意点をしっかりと理解しておくことで、補助金制度の手続きがスムーズに進められるでしょう。
ここでは空き家解体の補助金制度を利用する際の注意点について4つ紹介します。
1つ目は、地域や自治体によって制度が変わることです。
日本全国の市町村で実施されている補助金制度ですが、一律で決まった補助金が与えられるわけではありません。
ご自身が利用したい補助金が定まっていても、その地域の自治体に確認を取らなければ、費用負担に狂いが生じてしまう可能性があります。
補償内容や支給額も異なるケースは多いので、ご自身だけで判断しないようにしましょう。
2つ目は、審査には時間がかかることです。
多くの自治体が実施している空き家解体の補助金ですが、審査に通らなければ適用できない場合もあります。
審査では自治体の担当者が空き家の老朽具合を観察するため、一定の期間が必要です。
したがって、補助金の申し込みをすれば、即座に補助金が手に入るとは限らないのです。
3つ目は、可能な限りご自身で手続きを行うことです。
場合によっては、建設会社や解体業者が代行して、補助金の手続きを進めてもらえることも少なくありません。
しかし、代行して手続きを行ってもらうことで、手数料として補助金から数割程度差し引かれる可能性があります。
そのため、補助金を全額利用したい方は、ご自身で手続きを進めることをおすすめします。
4つ目は、補助金は後から支払われることです。
補助金を利用して解体工事の手続きを進めたいとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
領収書や証明書などを提出して初めて、補助金の受け渡しを行います。
つまり、工事の最初の時点ではご自身が全額を負担する必要があります。
□まとめ
今回は空き家解体費用に利用できる補助金制度について紹介しました。
空き家にはさまざまな解体費用の補助金を利用できますが、自治体によっては補償内容が異なることを押さえておきましょう。
当社では、お客様の不動産売買を全力でサポートしております。
空き家でお悩みの方はぜひ当社へご相談ください。
2022.12.02
不動産コラム
不動産売却では、さまざまな難しい専門用語が存在します。
しかし、これらの専門用語を理解していなければ、不動産売却でトラブルになってしまう可能性があります。
今回は、難しい専門用語の中でも任意売却と債務整理について解説していきます。
ぜひこの機会に両者の違いについて押さえておきましょう。
□任意売却と債務整理の違いとは?
*任意売却とは
任意売却とは住宅ローンの返済が困難になってしまった際に、債権者の同意のもと、不動産を売却する手続きのことを言います。
一般的な不動産売却とは異なり、不動産の売却代金を住宅ローンの残高に充てる必要があります。
つまり、任意売却は住宅ローンの残高を支払うために行う不動産売却です。
*債務整理とは
債務整理とは住宅ローンの返済し続けることが苦しくなった場合に、債権者と話し合い、借金やローンを減額してもらうことで返済していく方法を見つけることです。
したがって、債務整理は支払いが苦しくなった住宅ローンの返済をするための方法を見つけることであるため、任意売却が失敗してしまった次のステップとして債務整理があるのです。
また、債務整理は司法書士や弁護士に依頼して、債務者との交渉をしてもらうことが一般的です。
□債務整理するための選択肢は何がある?
ここでは債務整理の方法を以下の通り4つに分けて紹介します。
・自己破産
・任意整理
・特定調停
・個人再生
まずは、自己破産についてです。
自己破産とは、住宅ローンの支払いが不可能な状態にある際に、全て価値のある財産を精算することで借金を免除してもらうことです。
裁判所からは破産宣告を受けるため、ほとんどの財産を失うことになるものの、借金もゼロになることが特徴です。
職場を失ったり、病気で就職が難しくなったりして、ローンの返済が困難になってしまった際は、自己破産をすることが最善の選択とも言えるでしょう。
ただし、ギャンブルや投機などで生じた借金は免責の対象には含まれませんので注意する必要があります。
また、最長で10年間はクレジットカードや金融機関からの融資が受けられないことも留意しておきましょう。
次に、任意整理について紹介します。
任意整理とは、借金を額が少ない際に債権者と話し合うことで債務を整理する方法です。
この方法は、連帯保証人がいるケースといった少し複雑な関係にある不動産を売却する際には、効果的な債務整理であると言えます。
しかし、任意整理はローン返済額は圧縮されるものの、借金がなくなるわけではありませんので、十分な収入が得られる方でなければ利用できません。
加えて、おおよそ7年間はクレジットカードを持てなかったり、融資を受けられなかったりする恐れがあるため、注意しておきましょう。
そして、特定調停について説明します。
特定調停は、住宅ローンの返済が苦しくなってしまった方に、債権者と話し合い、裁判所によって今後の生活の立て直しを図る手続きのことです。
任意整理とは異なり、特定調停は弁護士を介さず、借り手と貸し手が直接話し合いを行います。
話し合いが上手くいけば、債務が圧縮される可能性もあります。
ただし、特定調停は一定金額の返済を前提としているため、収入がほとんど見込めない場合には利用できません。
最後に、個人再生についてです。
個人再生とは、裁判所を通して借金を減額してもらう手続きのことです。
裁判所に多岐に渡る必要書類を提出する必要があるので面倒に思う方もいらっしゃるかも知れませんが、任意整理と比較しても債務を大きく減額できることがメリットとして挙げられます。
しかし、住宅ローンには適用できませんので注意しましょう。
□任意売却で債務整理した解決事例とは?
1つ目の事例は、任意売却した後に自己破産を行ったケースです。
ある方は、住宅ローンの返済が困難になってしまったことから、任意売却を検討するようになったそうです。
担当の不動産会社からは返済に充てられる程度の売却益を見込めるだろうと言われていたものの、実際には何度も値下げを余儀なくされたのです。
その結果、住宅ローンの残高を下回る売却益となってしまい、残額は自己破産をすることで債務をゼロにしました。
2つ目の事例は、任意売却で借金を完済し、解決したケースです。
家計的に住宅ローンの返済が難しくなってしまったことにより、任意売却と自己破産を検討するようになりました。
そこでは、任意売却が成功したことにより、住宅ローンの残高を上回る金額で売却益を得ることができました。
したがって、自己破産をせずに任意売却のみで借金をゼロにできたのです。
これらの2つの解決事例からお分かりいただけるように、任意売却をした後に自己破産を行うことが肝であると言えます。
任意売却した後に自己破産する方が、ご自身の財産を手放さなくて済む確率が高いためです。
□まとめ
今回は、任意売却と債務整理の違いについて紹介しました。
当社では、任意売却を含めた不動産売却や買取を行っております。
お客様一人ひとりに合った方法で相談を承っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
2022.11.25
不動産コラム
何らかの事情で相続人がいないケースは存在します。
相続人のいないケースとしては、相続人が相続放棄したことや内縁関係にあることなどさまざまです。
そこで、今回は空き家の相続人がいないケースやその対処法について紹介していきます。
不動産相続の際にぜひ参考にしてくださいね。
□相続人のいないケースとは?
たいてい、被相続人が亡くなると、遺言書によって指定された「指定相続人」や法律上で定められた「法定相続人」に財産が相続されます。
しかし、何らかの要因で相続人がいないケースとして、主に以下のことが挙げられます。
・相続人が全員相続放棄をしたケース
・相続人が行方不明になったケース
・遺言がなく、法定相続人がいないケース
・相続人が相続欠格、廃除になったケース
・遺言がなく、内縁関係があるケース
それぞれ順に説明していきます。
1つ目は、相続人が全員相続放棄をしたケースです。
被相続人の財産の中に負債が多い場合は、財産を受け継ぎたくないと考える相続人もいるでしょう。
そのような方々が相続放棄をすると、相続人がいない状態になるのです。
2つ目は、相続人と連絡が付かなくなってしまったケースです。
相続人と全く連絡が取れなくなった場合は、相続人がいない扱いになります。
もし仮に、相続人が行方不明になって7年以上が経過してしまうと、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることで、相続人が存在しない状態にできます。
3つ目は、遺言がなく、法定相続人がいないケースです。
被相続人が遺言を残していなくて、法定相続人がいない事例でも相続人がいない状態になります。
被相続人の中に亡くなった被相続人と特別親しい関係にあった人や債権者がいる場合には、裁判所で相続財産管理人の選任の手続きができます。
しかし、これらに該当する方がいない際には、相続財産は国庫に帰属されます。
4つ目は、相続人が相続欠格、廃除になったケースです。
遺言書を捏造したり、不法廃棄したりするなどの違法行為をした相続人が「相続欠格」になってしまうケースがあります。
また、何らかの事情で被相続人が、遺言によってある相続人を「相続排除」することができます。
その結果、相続人がいない状態になるのです。
5つ目は、遺言がなく、内縁関係があるケースです。
被相続人と共に過ごし、特別親しい関係にあった「特別縁故者」であっても法定相続人の対象にはなりません。
遺言書に特別縁故者の氏名が書かれている場合には相続人に該当しますが、遺言書が存在しない場合には相続人がいない扱いになります。
□空き家の相続人がいない場合の対処法とは?
家を相続する際に、相続人がいない場合には、第三者に財産分与することができます。
親族ではない第三者に財産分与する場合には、遺言書が必要になるので用意しておく必要があります。
また、前述した通り、遺言で指名する際には特別縁故者である必要はなく、内縁関係にない方にも相続できます。
ただし、遺言書に関して法律上のルールに従っていなければ無効になるケースも存在します。
遺言書には以下の通り3種類が存在し、それぞれの必要な手順は異なります。
・自筆で作成する「自筆証書遺言」
・役場の公証人が作成する「公正証書遺言」
・内容を内密にする「秘密証書遺言」
これら3種類の中でも自筆証言遺言は簡単に作成できるので、遺言書を作る際にはおすすめです。
□空き家を放置することで起きるリスクとは?
*老朽化が進行する
放置された空き家では老朽化が進み、草木が生い茂ってしまいます。
庭にある植物が近隣の敷地内に入ったり、老朽化した建物に危険を感じさせたりと近隣住民に多大な迷惑をかけてしまいます。
*倒壊や放火される
地震や台風などの自然災害で空き家が倒壊してしまったり、放火犯による火災などで近隣の建物を損傷、延焼させてしまったりする恐れがあります。
近隣住民に被害を与えてしまうと、損害責任に問われる可能性も高くなります。
これらを予防するために火災保険に加入されている方もいらっしゃるでしょう。
しかし、住まなくなった空き家は一般物件扱いになってしまいますので、保険料が高く付いてしまいます。
*行政代執行により取り壊し費用が請求される
2015年の2月26日に施工された「空き家対策特別措置法」によって、放置された空き家が「特定空き家」に指定されることがあります。
特定空き家とは、そのまま放置しておくと、近隣へ衛生上の危険があると判断された空き家のことです。
この特定空き家に指定されると、行政代執行によって強制撤去されます。
そして、撤去された後は、取り壊し費用の請求が来ます。
□まとめ
今回は、空き家を相続する際に、相続人がいないケースについて紹介しました。
相続人がどうしてもいない場合には、遺言書を作成しておくと安心です。
当社では、不動産売却や買取を取り扱っております。
空き家売却を含め、不動産売却や買取りに関してご不明点がある際は、ぜひ当社へご相談くださいね。
2022.11.15
不動産コラム
「任意売却を検討しているけれど、どれくらいの期間がかかるのか分からない」
「任意売却を進める手順を知りたい」
このように考えている方は、多くいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、任意売却の流れや期間、売却のタイミングについて解説します。
また、任意売却で早く売却するコツも併せて紹介していきます。
□任意売却の流れや期間とは?
任意売却とは何らかの理由で住宅ローンを支払えず、一般的な売却では残高を返済できない際に、債権者に条件付きで許可をもらい、抵当権を抹消して不動産を売却する方法です。
そこで、任意売却の流れは以下のような8つのステップがあります。
・金融機関から督促状が送られる
・不動産会社に査定を依頼する
・住宅ローンの残高を確認する
・債権者から任意売却を行う許可をもらう
・任意売却の手続きを進める
・売買契約が成立した後は購入者が決済を行う
・所有権を移行する
・新生活が始まる
大まかな期間として、任意売却は全体的な手続きで約10ヶ月ほどかかります。
金融機関から督促状が送られ、任意売却の売買が始まるまでは約6ヶ月から9ヶ月、売買契約が成立してから新生活が始まるまでは1ヶ月程度かかります。
そこで、それぞれの流れについて順に解説していきます。
まずは、金融機関から督促状が送られます。
督促状とはローンの支払いができない場合に金融機関から支払いを督促されるハガキや電話のことを言います。
督促状が届いたら、できるだけ早く不動産会社に相談して査定を行ってもらいましょう。
不動産会社による査定が完了した後は、住宅ローンの残高を把握するとともに債権者から任意売却を行う許可をもらう手続きを進めましょう。
しかし、売却価格と住宅ローンの残高に大きな差があった場合や、計画性が全くないと判断された場合には任意売却の許可がおりないケースがあります。
債権者との交渉を円滑に進めるためにも、不動産会社としっかりと話し合いや打ち合わせをしておきましょう。
任意売却の許可がおりたら、実際に手続きと売買をスタートさせます。
手続きに必要な書類は複数存在するので、不動産会社に確認をとっておきましょう。
そして、購入者が決定すると後は決済を待つだけです。
最後に所有権を移行させたら、新しい生活が始まります。
所有権の移行は、司法書士が代行して行ってくれるケースがほとんどですので、1週間から2週間ほど待ちましょう。
□任意売却のタイミングはいつ?
結論から申しますと、任意売却のタイミングは住宅ローン返済を滞納した時です。
そもそも、ローン返済が滞納していなければ任意売却はできません。
これは返済がどんなに苦しい時であっても、滞納していなければ同様です。
そこで、ローン返済が苦しく、期限の利益が失効したタイミングに任意売却の手続きを始めましょう。
期限の利益とは、債務者が返済の期限が到来するまで返済をしなくても良いという権利です。
このようなタイミングであれば、競売の申し立てに半年程度の売却期間が設けられることもあります。
まずは、任意売却を円滑に進めるためにも、お早めに不動産会社に相談しましょう。
□任意売却で早く売るコツを教えます!
これまで、任意売却の流れと期間について紹介してきましたが、できるだけ早く売りたいと感じた方も多くいらっしゃるでしょう。
実際に、任意売却で早く売るコツは3つあります。
・返済が困難だと感じた時点で不動産会社に相談する
・不動産会社による買取りを利用する
・業績のある不動産会社に依頼する
1つ目は、返済が困難だと感じた時点で不動産会社に相談することです。
これは、住宅をいち早く売却するための重要事項とも言えます。
あらかじめ早い段階で不動産会社に依頼しておくことで、今後の手続きがスムーズにいき、競売にかけられる可能性も低くなります。
2つ目は、不動産会社による買取りを利用することです。
一般的な売却と同様に、住宅を早く売却するには買取りを利用すると良いでしょう。
買取りとは直接不動産会社が物件を買取ることです。
そのため、仲介とは異なり、新たな買主を探す手間が省けて早い段階で住宅を売却できます。
ただし、仲介と比較しても買取りは安い売却価格になってしまうケースがほとんどです。
そのため、債権者が任意売却の許可をしてくれないといった事態になる恐れもあるので、話し合いは必ず行っておきましょう。
3つ目は、業績のある不動産会社に依頼することです。
任意売却を短期間で行うためにも、任意売却の業績があり信憑性の高い不動産会社に依頼することがとても重要です。
当社では、仲介や買取りに加えて任意売却におきましても数ある業績を残しております。
お客様のニーズに合わせたスピーディーな対応も心掛けておりますので、ぜひ安心して一度ご相談ください。
□まとめ
今回は、任意売却の流れや期間、タイミングについて紹介しました。
今回の記事で任意売却について、理解を深めていただけましたら幸いです。
お気軽に当社へお問い合わせくださいね。
2022.11.08
不動産コラム
相続する遺産分割の割合にはいくつかの種類があり、それぞれ十分に理解していなければトラブルに発展してしまう恐れがあります。
そのようなトラブルを未然に防ぐためにも、今回は遺産分割の割合の決め方について解説します。
加えて、特殊なケースでの遺産分割についても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
□相続する遺産の分割の割合は?
遺産分割の割合において、民法の規定に基づいた以下のような手順で行われます。
・遺言
・遺産分割協議
・法定相続分
まずは、遺言がある際にはその遺言の内容に従って相続分を決定します。
遺言で相続人に遺贈する方法は2つのパターンが存在し、それは「包括遺贈」と「特定遺贈」です。
包括遺贈とは、遺産分割の割合を決定して遺贈する方法です。
一方で、特定遺贈はある特定の遺産を特定の相続人に遺贈する方法です。
つまり、両者の違いは割合を決定して相続するかしないかということになります。
次に、遺言がない場合は遺産分割協議で相続する割合を決定します。
相続する遺産は全相続人が共有するものと定められており、相続人は原則いつでも遺産分割協議によって相続分を決定できます。
そして、この遺産相続協議では後に紹介する法定相続分に関係なく、自由に遺産を分割できるのが特徴的です。
それゆえ、相続人の間で同意さえあれば、どのように相続分を決定しても良いのです。
しかし、遺産相続協議でも相続分が決定しないケースは少なからず存在します。
仮に相続分が決まらなかった場合には、法定相続分で決定します。
法定相続分とは、各相続人の取り分として法律上定められた割合のことを指し、これは最終的な相続割合を決定するための基準となります。
相続する割合と聞けば、真っ先に法定相続分をイメージする方が多いのですが、遺言や遺産分割協議でも定まらなかった際に、法定相続分に基づくということを念頭に置いておきましょう。
□相続人別の相続割合とは?
これまでは相続分の割合の決定に関して解説しましたが、相続人別の割合について知りたいと思っている方も多くいらっしゃるでしょう。
実際に、相続人によって遺産分割する割合は異なります。
ここでは、以下の4つのケースに分けて、相続人別の遺産分割の割合に関して紹介します。
・配偶者のみ、子どものみ、両親のみ、兄弟姉妹のみの時
・配偶者と子どものみの時
・配偶者と親のみの時
・配偶者と兄弟姉妹のみの時
まずは、配偶者のみ、子どものみ、両親のみ、兄弟姉妹のみの時に関してです。
上記のように、ある1種類の相続人しかいない場合にはその相続人が全ての財産を相続することになります。
また、兄弟や子供が複数人の場合にはそれぞれ等分した割合が相続されます。
次に、配偶者と子どものみの時に関してです。
配偶者と子どものみが相続人になる際には、それぞれ半分ずつ相続されます。
ただし、子どもが2人いる場合には、配偶者にはそのまま2分の1が相続され、子どもには各々4分の1ずつが相続されます。
そして、配偶者と親のみの時に関してです。
配偶者と親が相続人になる場合は、配偶者は3分の2、親には3分の1が相続されます。
これも同様に、両親が存命の際には3分の1をさらに半分にした6分の1ずつが各々の相続分の割合です。
最後に、配偶者と兄弟姉妹のみの時に関してです。
配偶者と兄弟姉妹のみが相続人の際には、配偶者が4分の3、兄弟姉妹に4分の1が相続される割合です。
□特別なケースの相続に関して解説します!
ここでは、「被相続人に借金がある場合」と「誰かが相続放棄した場合」の2つの特殊なケースの相続に関して解説していきます。
*被相続人に借金がある場合
相続することはプラスの資産だけをイメージしがちですが、遺産相続ではマイナスの資産、つまり借金も相続人が背負うことになります。
相続分は先ほど紹介した法定相続分の割合と同じです。
どうしても借金を相続したくない際には、プラスの資産だけを相続する限定承認を利用することや、相続放棄を検討した方が良いでしょう。
*誰かが相続放棄した場合
相続人は、相続を放棄できる権利があり、これを相続放棄と言います。
相続放棄は、被相続人に多額な借金があったり、相続に関するトラブルに巻き込まれたくなかったりした場合に行うのが一般的です。
もし、相続人である誰かが相続放棄をした場合には、相続放棄した相続人を除いた相続人で法定相続分に基づいて決定します。
例えば、子ども3人のみの相続でその内1人が相続放棄した場合には、残りの2人で2分の1ずつ相続することになります。
しかし、相続放棄は相続を知ってから3ヶ月以内という期限が設けられているので注意する必要があります。
□まとめ
今回は遺産分割の割合と法定相続人別の相続割合について解説しました。
当社では、お客様の不動産売買を全力でサポートしております。
まずは、相続についてお悩みの方もまずはお気軽に当社へご相談ください。
2022.11.01
不動産コラム
「空き家は掃除した方が良いのか分からない」
「空き家の清掃にかかる費用を抑えたい」
このように、お考えの方は少なからずいらっしゃるでしょう。
そこで、今回は空き家の清掃について解説していきます。
また、清掃費を抑えるポイントや掃除しないまま放置することで生じるリスクも併せて紹介します。
□空き家の清掃方法とは?
空き家を高く売却するためには、資産価値を維持するために定期的に清掃する必要があります。
放置したままの空き家の劣化スピードは非常に早いので、掃除しようと思ってもどこから始めたら良いか分からないとお悩みの方もいらっしゃるでしょう。
ここでは、空き家の清掃方法について、自身で行う方法と業者に依頼する方法の2つのパターンについてご紹介します。
*自身で清掃する
自身で清掃するケースでは、家の中の片付けを全て1人で行う必要があるので一日で完了することは非常に困難です。
また、家の中の清掃のみならず、家の外構や庭を設置している方はそれらの手入れも視野に入れておきましょう。
もし、仕分けや不用品処分、掃除を一人で行うことに抵抗がある方は、次に紹介する業者に依頼する方法を参考にしてください。
*業者に依頼する
ここで紹介する業者とは、空き家掃除に関する会社やハウスクリーン会社を指します。
これらの業者に依頼することで、家の中や外構の清掃をしてくれるので、一人で掃除をする分の負担が軽減されます。
ただし、依頼する業者によっては清掃のプラン内容や費用が異なります。
そのため、サービス内容をしっかりと確認し、予算に合う清掃プランを依頼することがとても重要です。
□空き家の清掃費を抑える方法とは?
清掃費の相場を確認する上で、もう少し費用を抑えたいとお考えの方も少なくないはずです。
実際に、空き家の清掃費を抑える方法はあります。
ここでは以下の2つのポイントを紹介します。
・可能な限り自身で掃除をしておく
・見積もりを細かく出す
1つ目は、可能な限り自身で清掃をしておくことです。
ほとんどの清掃業者は片付けにかかった時間、人数、間取りをもとに料金を決定します。
そのため、あらかじめ自身で清掃をしておくことによって、業者が必要とする時間や人数を減らせるので費用を少なくできる可能性が高まります。
簡単に片付けられる箇所は、片付けておきましょう。
とは言っても、どのように清掃すれば良いのか分からないという方もいらっしゃるでしょう。
そのような方には、簡単な清掃を「保管するものと処分するものを分けておく作業」と考えていただいても問題ありません。
保管するものと処分するものを分けておくだけでも、費用を抑えられる可能性は高まります。
加えて、清掃を1人で行うのではなく、友人や知り合いにも手伝ってもらいましょう。
2つ目は、見積もりを細かく出すことです。
いち早く空き家の清掃をするために、見積もりをしっかりと確認せずに業者に依頼する方もいらっしゃいます。
見積もりの内容を十分に確認しないことによって、後にさまざまなトラブルに巻き込まれる恐れがあります。
例えば、最初は安い金額で提示されたものの、追加料金で費用がかさばったり、実は必要のないサービス内容が入っていたりするケースです。
このように、見積もりを確認しないだけで、余計に費用がかかる場合もあるので注意しておきましょう。
□空き家を放置することで起きるリスクとは?
空き家を放置することで、以下の5つのリスクが考えられます。
・不法投棄
・放火
・被災
・犯罪
・多大な税金
1つ目は、不法投棄が行われることです。
空き家の庭に粗大ゴミを不法投棄されるケースは少なくありません。
このように不法投棄されると、実は空き家の持ち主にゴミを処分することが求められます。
2つ目は、放火が行われる恐れがあることです。
放火による犯罪に関して、空き家が狙われるケースは多いのです。
これによって最も恐れるべきなのは、空き家の周辺に建てられているお住まいが火災に巻き込まれることです。
空き家を放置していると、多額な賠償金を支払う必要があります。
3つ目は、被災する可能性があることです。
定期的な掃除をしていない空き家では、劣化スピードが非常に早くなります。
これにより、台風や大雨などが原因で家が崩壊することや、隣家に被害を与えてしまう可能性もあります。
4つ目は、犯罪が行われた際に関与が疑われる場合があることです。
暴行といった犯罪は、人目がない空き家で行われることが多いのです。
犯罪の罪に問われることはありませんが、事件との関与が疑われるかもしれませんので注意しましょう。
5つ目は、多大な税金がかかることです。
特定空き家に指定された際には、固定資産税を通常の6倍の額で支払う必要があります。
特定空き家とは、国が倒壊などのリスクがあると判断した空き家のことを言います。
日々の清掃を怠っていると、特定空き家に指定される可能性は高まりますので、できるだけ早く売却しましょう。
□まとめ
今回は、空き家の清掃方法と清掃費を抑える方法、空き家を放置することで生じるリスクについて紹介しました。
空き家を放置することはリスクでしかありません。
そのため、空き家はいち早く売却するようにしましょう。
空き家の売却は、ぜひ当社にお任せください。
2022.10.25
不動産コラム
たくさんの思い出が詰まっている実家を売却することによって、少し寂しい気持ちになるかもしれません。
ただし、実家を放置することで犯罪に巻き込まれる可能性があり、多大な税金を支払う必要もあります。
今回は、実家を売却する手順や売却する前に押さえておくべきポイントを紹介していきます。
□実家を売却する手順とは?
実家を売却する流れとしては以下のような8つのステップに基づいて行います。
・相続登記
・査定
・媒介契約
・販売活動
・内覧
・価格、取引条件の交渉
・売買契約
・引き渡し、決済
はじめに行うステップは相続登記です。
相続登記とは不動産の所有者の名義変更のことです。
実家を相続した後であっても、登記簿謄本には被相続人の名義になっているケースがほとんどです。
不動産はその所有者のみ売却できるので、登記簿謄本が被相続人のままだと売却できません。
次に、査定を行います。
相続登記が完了したら、不動産会社に依頼して査定を行ってもらいましょう。
仮に査定額が高くても、実家の状態によっては売れ残る可能性もあるので留意しておきましょう。
査定をして不動産会社を決めた後は、その不動産会社と媒介契約を結びます。
媒介契約とは、不動産会社に仲介として実家の販売を任せてその報酬として、仲介手数料を支払うといった契約です。
一般的に媒介契約には、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類があるので、それぞれ確認しておきましょう。
そして、販売活動を行います。
媒介契約を結んだ不動産会社が物件広告を作成したり、販売営業や内覧準備を進めたりします。
いつ内覧をしても良いように、部屋の掃除や整理は心がけておきましょう。
販売活動の次は内覧に移ります。
不動産会社が物件広告を出すと、一日に多数の内覧の申し込みが来ることがあります。
不動産会社とスケジュールを調整して、可能な限り日光が入りやすい時間帯に内覧を実施しましょう。
内覧が完了すると価格、取引条件の交渉を行います。
内覧時に好印象だった相手でも、大幅な値下げ交渉をしてくるケースもあります。
このようなケースに備えて、あらかじめ値下げの最低ラインを定めておくと良いでしょう。
価格、取引条件の交渉が成立したら、売買契約を結びましょう。
売買契約を行う当日は、売主と買主、不動産業者で契約事項を確認していきます。
ここでは契約書に、契約内容がしっかりと書かれているか注意しておきましょう。
最後に、引き渡しと決済を行います。
買主からお金を支払ってもらい、さまざまな費用の清算をして引き渡しは終了します。
□実家を売却する前に押さえておくべきポイントとは?
実家を売却する前にしておくこととしてポイントが3点あります。
・実家の片付け
・仏壇やお墓のお引っ越し
・税金対策
*実家を片付ける
実家を処分すると決まれば、遺品整理をする必要があります。
実家を片付ける方法として、自身で行う方法と業者に依頼する方法の2つのパターンがあります。
まずは、自身で行う方法についてです。
自身で片付ける場合は、あらかじめ処分するものと保管するものを分けておくとスムーズに進みます。
しかし、多大な時間を要することになるケースもあるので注意しましょう。
一方で、業者に依頼すると実家の遺品整理から掃除まで行ってくれます。
費用は高くなりますが、負担が大幅軽減されるので、自身で片付ける余裕がない際には業者に依頼すると良いでしょう。
*仏壇やお墓のお引っ越し
実家を処分する直前に思い浮かべがちなのが、仏壇やお墓のお引っ越しです。
仏壇やお墓を容易に移動させることは困難でしょう。
また、これには特殊な運搬や手続きに加えて、特別な供養をする必要があるので、必ず事前に確認しておきましょう。
*税金対策をする
実家を売却する際に、売買契約書等の家を購入する時にもらう資料があると、経費算入ができる可能性があるので税金を抑えられます。
節税を期待して、実家を購入した際にもらう資料を今のうちに集めておきましょう。
□実家を売却するなら3年以内に!
実家を売却するなら、3年以内に手続きを行いましょう。
3年以内に売却する理由をそれぞれ紹介します。
1つ目は、節税できることです。
家の資料を集めるだけでなく、早く売却することも節税効果を見込めます。
特に、3年10ヶ月以内に実家を売却した際には、取得費加算の特例に該当するので譲渡所得税が安くなるのです。
2つ目は、維持費を削減できることです。
空き家になる実家を保有しているだけでも、固定資産税や修繕費、管理委託費の3つの費用がかかります。
実家に住む予定がない方は、できるだけ早く売却手続きを行いましょう。
3つ目は、高く売れやすいことです。
年月が経てば経つほど、不動産の資産価値は大幅に減少していきます。
遅い段階で売却すると、最悪売れない事態になってしまう恐れもあるので注意しましょう。
□まとめ
今回は、実家を売却する手順や売却する際のポイントなどについて紹介しました。
当社では、お客さまの不動産売買を全力でサポートいたします。
安心して実家の売却をしたい方は、ぜひ当社へご相談くださいね。
2022.10.16
不動産コラム
みなさんは子どもや親、孫がどれくらいの相続分を持っているのか、知っているでしょうか。
相続の決まりは非常に複雑ですから、細かく理解している方は少ないのではないでしょうか。
そこでこの記事では、法定相続人や半血兄弟姉妹の相続分について解説します。
□法定相続人とは?
法定相続人とは、民法によって規定されている相続人のことです。
つまり、相続財産を継承する人のことを指します。
法定相続人には、必ず相続人となる配偶者と、順位によって相続人になる子や親のような血族がいます。
では、血族はどのようにして順位が決まるのでしょうか。
血族は第一順位、第二順位、第三順位の順番で相続人となります。
第一順位には、子(実子、養子、胎児)がきます。
第一順位の血族がいない場合には、第二順位である直系尊属がきます。
直系尊属とは、父母や祖父母のように自分より前の世代で、直通する系統の親族のことです。
第一順位と第二順位の血族がいない場合、第三順位である兄弟姉妹がきます。
では、これらの相続人にどれくらいの財産が振り分けられるのでしょうか。
ここでは相続割合を示す法定相続分について解説します。
法定相続分とは、民法に規定されたそれぞれの相続人が、相続財産に対して持っている所有割合のことを言います。
もし被相続人の遺言がなく、相続人が複数存在するのであれば、残された財産は法定相続人で共有している状態になります。
では、現在の民法では法定相続分はどのように規定されているのでしょうか。
法定相続分をまとめると以下の通りです。
まずは、配偶者と子のみの場合です。
この場合、配偶者と子でそれぞれ半分ずつ財産を分け合います。
しかし、子どもが複数存在する場合、子どもの財産は頭数で等分することになっています。
次は、配偶者と直系尊属の場合です。
この場合、配偶者には3分の2の財産が割り振られ、配偶者以外の相続人にはそれ以外が割り振られます。
最後は、配偶者と兄弟姉妹の場合です。
配偶者には4分の3の財産が分配され、配偶者以外の相続人にはそれ以外の4分の1が分配されます。
□半血兄弟姉妹とは?
ここで半血兄弟姉妹についても解説しておきましょう。
半血兄弟姉妹とは、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹のことです。
あまり聞きなじみのない言葉ですよね。
例えば、離婚した父親が時間が経ってまた再婚して、その再婚相手との間にできた妹がいたとします。
これを半血兄弟姉妹といいます。
いわゆる異母兄弟のことで、こちらは耳にすることもある言葉ですよね。
どちらにしても、血が繋がっている兄弟姉妹ですから、亡くなった方に子や直系尊属がいなければ、相続人になり得るわけですね。
□半血の兄弟の相続分はどれくらい?
半血兄弟姉妹について解説しました。
ここまでで気になるのが半血兄弟姉妹の相続分ですよね。
ここからはわかりやすくするために、相続の状況をシミュレーションしながら考えていきます。
まず、被相続人には配偶者はおらず、兄A、妹B、半血の弟Cがいたとします。
また、被相続人の母と父、後妻は亡くなっていると想定しましょう。
結論から申し上げますと、このケースでの相続分は以下のようになります。
・兄Aの相続分は全体の5分の2
・妹Bの相続分は全体の5分の2
・半血の弟Cの相続分は全体の5分の1
つまり、被相続人の財産が2000万円だった場合、兄Aは800万円、妹Bは800万円、半血の弟Cは400万円の財産を相続することになるのです。
被相続人の相続分は配偶者が優先されますが、このケースでは配偶者がいないという想定なので、兄弟姉妹が全て相続することになっています。
この具体例からわかっていただけるように、半血の兄弟姉妹の法定相続分は全血の兄弟姉妹の法定相続分の半分になります。
ただ、このケースでは被相続人の子や孫のような直系卑属、親のような直系尊属がいないことを想定していますので注意してくださいね。
ご自身の場合だと、どうなるかもぜひ考えてみてください。
ここで注意点をいくつかご紹介します。
それは全血の兄弟姉妹と半血の兄弟姉妹の相続分について問題になるのは、あくまでも第三順位の兄弟姉妹の相続の場合であることです。
つまり、第一順位の子として相続人になる場合は、全血と半血の区別が発生せず、法定相続分は同じになります。
また、嫡出子と非嫡出子の相続に関しても注意が必要です。
平成25年の9月に非嫡出子に対する相続差別が意見とみなされ、差別規定を削除する決定がなされました。
具体的には、嫡出でない子の相続分は嫡出である子の相続分の2分の1とされていた規定が改正されたのです。
□まとめ
法定相続人とは何かというところから、半血兄弟姉妹の相続分がどうなるのかについてまで解説しました。
相続は複雑なルールで規定されているので、相続について理解するのは非常に時間がかかります。
しかし、時間をかければ必ず理解できる内容ですので、ぜひ調べてみてくださいね。
2022.10.09
不動産コラム
「土地を子どもに譲るか、売却してしまうかで迷っている」
「土地を譲渡する際に気をつけておくべきことを知りたい」
このように思っている方は多いでしょう。
そこでこの記事では、土地を子どもに譲渡するのか、売却するのかどっちの方が良いのかを解説します。
□土地を子どもに譲渡するか売却するかどっちが良い?
土地をどのように取り扱うのかというのは難しい問題ですよね。
ここでは子どもに譲渡するか、売却するかを金銭的な観点からケースに分けて解説します。
*子どもに譲渡する場合
土地を子どもに譲るとなると、贈与税がかかります。
一般的な贈与の場合、税金がかからない基礎控除額は110万円です。
一方で相続の場合の基礎控除額は、法定相続人の数に600万円をかけ、そこに3000万円を足すことによって求められます。
つまり、相続税よりも贈与税の方が高くなるということですね。
しかし、子どもが成人していて、かつ親の年齢が60歳以上であれば、「相続時精算課税制度」が利用できます。
これは2500万円まで贈与税を納めずに贈与できるという制度です。
それ以上になった場合は、一律20パーセントの贈与税が課されます。
贈与をしてから親が亡くなると、譲った土地は相続財産として相続税を計算し、すでに納められている贈与税分が相続税から除かれます。
つまり、税金を支払う時期が相続時まで延ばされる制度です。
税金を払わなくて良くなるわけではないので注意してくださいね。
なお、子どもに土地を譲渡する場合は、登録免許税と不動産取得税を払う必要があることを知っておいてくださいね。
*売却する場合
一方で売却する場合はどうでしょうか。
売却して利益を得た場合は、所得税を納める必要があります。
子どもに譲渡する場合と異なった税金が必要だということですね。
しかし、その土地を購入した価格よりも安い価格で売れた場合は税金は不要です。
もし土地を売らずにそのまま持っていた場合は、問題が起こる危険性があります。
それは相続問題です。
親が亡くなった際、兄弟で共同で土地を所有していた場合、分割するのは難しいですよね。
遺産分割協議でトラブルに発展する可能性があるので、売却して現金化すると良いでしょう。
ここまで2つのケースに分けて解説してきましたが、どちらの方が税金が高くなるのか、わからないですよね。
そのような時は不動産会社に査定依頼すると良いです。
当社でも査定を行っておりますので、ぜひご相談ください。
□親族間売買について解説します!
先ほどの前半のケースで親子間での不動産のやりとりについて解説しましたが、税金の取り扱いには特に注意しなければなりません。
なぜなら、贈与と売買で納める税金の額が変わってくるからです。
ここでは親族間売買について解説します。
親族間売買とは、親と子の間で不動産を売買することです。
この場合、買主と売主で価格を自由に決められるため、相場よりずっと安い価格で取引できます。
これによって支払う税金の額を抑えられるのです。
しかし、注意点があります。
それは親族の範囲です。
どこからどこまでが親族なのかをしっかり把握していないと、親族間売買として扱われない可能性があります。
民法では、親族は6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族だと決められています。
ただ、税務署が考えている親族の範囲はここにとどまるわけではありません。
最も重視されるのは、相続税や贈与税逃れのための不動産売買ではないかということです。
□土地を譲渡する際の注意点とは?
次に土地を譲渡する際の注意点をいくつかご紹介します。
1つ目は、みなし贈与です。
先ほど、買主と売主で価格を自由に決められるため、相場よりずっと安い価格で取引できると申し上げましたが、あまりにも安い価格で譲渡すると、みなし贈与に認定されます。
例えば、実質2000万円の土地を100万円で譲渡したとすると、実際の価値よりも安すぎる価格で取引しているとみなされて、差額の1900万円に対して贈与税が課されてしまうのです。
2つ目は、親子への譲渡では、3000万円控除が適用されないことです。
3000万円控除を簡単に説明すると、譲渡した際にかかる税金を抑えるための制度です。
しかし、親族間で不動産の取引をする場合はこの制度が利用できません。
他にも、10年超所有軽減税率の特例も受けられませんので注意してくださいね。
3つ目は、親族間売買ではローンが通りにくいことです。
そのため、多くの方は分割払いを利用します。
分割払いを利用する場合は、支払い方法を売買契約書に記載する必要があるので、ぜひ覚えておいてくださいね。
□まとめ
土地の取り扱いについて、親子間で譲渡するのか、売却するのかの2つのケースに分けて解説しました。
それぞれのケースで必要になる税金の額を知るには、不動産会社に問い合わせてみてくださいね。
当社では、不動産売買のサポートをしておりますので、お悩みの方はぜひご連絡ください。
2022.10.02
不動産コラム
「相続登記に必要な書類には何があるのか」
「相続登記はどのような流れで行われるのか」
このように、相続登記について疑問をお持ちの方は多いでしょう。
この記事では相続登記での必要書類と流れを解説します。
□相続登記での必要書類をご紹介!
相続登記では、どのような書類が必要になるのでしょうか。
用意する必要がある書類は以下の通りです。
・相続人全員の戸籍謄本
・被相続人出生から死亡までの戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・不動産取得者の住民票
・相続する不動産の固定資産評価証明書
・収入印紙
・登記申請書
・返信用封筒
相続には3つのケースがあります。
それは「遺産分割協議による相続」「法定相続人による相続」「遺言による相続」です。
それぞれで必要な書類を詳しく解説していきます。
まずは、遺産分割協議による相続です。
遺産分割協議とは、相続人が集まってどのようにして遺産を分割するのかを話し合うことです。
全員が合意しないと相続登記できないため、しっかりと話し合いましょう。
遺産分割協議がまとまると、遺産分割協議書を作成して、相続人全員が署名し、実印を押します。
このケースでは先ほどご紹介した書類の他に、遺産分割協議書とそれぞれの印鑑証明書が必要です。
遺産分割協議書はご自身で作成いただき、印鑑証明書は市町村役場で発行できます。
次は、法定相続人による相続です。
法定相続分とは、民法上で定められた相続人の取り分の割合のことです。
この割合に沿って相続を行った場合、先ほどご紹介した書類だけで十分です。
追加で必要な書類はありません。
最後は、遺言による相続です。
被相続人の遺言によって法定相続人が不動産を得た場合、先ほどの書類に加えて遺言書が必要になります。
遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあります。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、家庭裁判所の検認手続きが必要です。
これは遺言書が本物なのかを調べる手続きです。
一方で公正証書遺言はこの必要がありません。
□相続登記の流れを解説します!
相続登記で必要になる書類を把握できたでしょうか。
ここからは相続登記の流れを解説します。
*相続人の間で土地の分割方法を協議する
不動産を相続するには、不動産の名義を被相続人から相続人に移す必要があります。
そのためにまずは、相続人同士で話し合って、誰の名義に変更するのかを決定しましょう。
遺産分割協議書を作成して、全員で署名・捺印します。
*相続登記の準備をする
もし相続財産に不動産が含まれている場合は、相続登記する必要があります。
先ほどご紹介した書類を用意して、相続登記の準備を始めましょう。
必要書類を全て揃えるのに時間がかかりますから、早めの段階から準備を始めることをおすすめします。
*集めた書類を法務局に提出する
最後に、集めた書類を記入して法務局に提出します。
このタイミングで登録免許税を法務局に納付しましょう。
法務局に書類を提出してから1週間から2週間で不動産の新しい権利証が発行されます。
これが発行されたら、相続登記は完了です。
ここまででわかっていただけたように、相続登記は時間がかかりますし、流れも複雑です。
時間に余裕がない方、問題なく進められるか不安な方は司法書士に依頼してみると良いでしょう。
□相続した土地はどのようにして分ける?
先ほど遺産分割協議によって相続した土地の分け方を話し合うと申し上げましたが、具体的にどのようにして分けるのでしょうか。
ここでは遺産を分割する方法である「現物分割」「換価分割」「代償分割」「共有分割」について詳しく解説します。
まずは、現物分割です。
例えば、土地のような不動産を兄に、預金のような現金は姉に分けるというやり方が現物分割です。
分割の仕方が非常にシンプルでわかりやすい点が特徴です。
しかしながら、分割の仕方に不公平感を感じる方が多いことがデメリットです。
次は、換価分割です。
これは遺産を売却して現金にしたのち、トータルの現金を相続分に応じて分割する方法です。
もし相続する財産が不動産だけであれば、それを売却してからその売却益を相続人同士で分割することになります。
これは先ほどの現物分割とは違って、売却できる財産であれば公平に相続できるでしょう。
しかし、売却時に譲渡所得税などの税金が発生するため、注意が必要です。
次は、代償分割です。
これは1人の相続人が全ての遺産を分割する代わりに他の相続人に対して、相続分に応じた金額を支払う分割方式です。
分割のしにくい財産であっても分割ができる点が魅力的な一方で、支払いをする側に代償金額を支払うだけの資金力が必要になります。
最後は、共有分割です。
これは遺産を相続人全員で共有する方式です。
不公平感をなくせることが最大の特徴だと言えるでしょう。
□まとめ
相続登記に必要な書類や流れ、遺産の分割方式について解説しました。
この記事を参考に、相続登記をスムーズに進めてくださいね。
お問い合わせ
CONTACT
「悩みがある・困っている・売りたい、買いたい」
何でもご相談ください!